不完全性定理入門 初級編:数式をなるべく使わない説明 ver.2023.02.23
1. 不完全性定理理解の第一歩に向けて…このテキストの内容の説明
このテキストでは、1931年にクルト・ゲーデルが発表した数学の定理である不完全性定理の理解への第一歩として、なるべく数式を使わない説明を行う。不完全性定理には第一不完全性定理と第二不完全性定理のふたつがあるが、最初、物理学の万物の理論とのアナロジーを使って、第一不完全性定理がどんな定理なのかを説明し(第2-8節)、その後で第二不完全性定理の説明、および、第一不完全性定理と第二不完全性定理が生まれた歴史的背景について説明する(第9-15節)。そして、最後にこの定理の人類の知の歴史における位置付けを行う(第16節)。
このテキストでは数式をなるべく使わないように試みたが例外的に第4節は数学の記号や式がかなり出て来る。ただし、この節は飛ばして読んでも読めるように書いた。また、ゲーデル数というものを説明するための第7節でも数式が少し出るが、簡単な数の計算の話で中学校の数学程度なので困難なく読めるはずだ。
また、このテキストは、雑誌「数学セミナー」2021年1月号に掲載された私の記事「数学基礎論 知の階層」(こちら)のコンセプトを元にして書いたが、このテキストの方がはるかに詳しい。
2. 数学の万物の理論:公理的集合論 ZFC, TG
20世紀初頭に相対性理論と量子論が生まれ物理学はその姿を大きく変え、原子力やITというそれ以前には想像もつかなかったようなテクノロジーを生んだ。本稿のテーマである数学も、19世紀末から20世紀初頭に集合論を使う抽象数学が誕生し、それまでとは全く違う姿になった。そして、数学の場合には、さらに「数学における存在論と証明方法についての統一的基礎理論」が誕生した。公理的集合論 ZFC と、その拡張の TG である。ZFC や TG では、自然数や複素数などの数、そして空間などを集合を使って定義できる。現代の数学的対象の存在論、つまり、どの様な数学的対象が存在するかは、これらの理論により規定されている。そして、それらの数学的対象について、どの様な事実(定理・命題)が成り立つかは、それに証明を与えることによって決定されるわけだが、その証明のために必要な証明方法は ZFC や TG が提供する証明方法で十分だと考えられている。つまり、現在までになされた数学のすべては、概念の定義と証明に限れば、 ZFC や TG という理論により、すべて再現できるし、これからの数学を行うにも、これらだけで十分だろうと考えられているのである。
今までの数学も未来の数学のすべても、定義と証明については、僅か10個程度の公理しか持たない ZFC や TG という理論で行える。この様なものを生み出したことは20世紀数学の大きな成果であり、そういうものが存在するということは、数学と言う学問に特有の驚くべきことである。これがいかに特殊で驚くべきことか、それはこれを物理学の場合と比べてみればわかる。
物理学ではミクロの世界の現象は量子論で、宇宙規模の現象は相対性理論で説明するのだが、この二つの理論は統一されていない。この二つの理論は、そもそもその基本思想が矛盾しているのである。そのため相対性理論の創始者のアインシュタインは量子論の考え方を認めず、EPRパラドックスと呼ばれる思考実験をして、なんとかそれを否定しようと努力したのは有名な話である。このパラドックスは現在では理論的に解決され実際に起こることが実験でも示されている。しかし、相対性理論と量子論の基本的な世界観が相容れないことには変わりがない。
そして、このことは実際の物理学研究の障害になっている。相対性理論で説明される広大な宇宙が、最初は量子レベルに小さかったとされるビッグバンのプロセスを解明できないのである。最初の極小宇宙はミクロの世界なので量子論が必要である。しかし、ビッグバンが起きて現在の様に巨大になった宇宙は相対性理論で説明される。では、この二つはどうやって繋がれるのだろうか、そういう問題が生じるのである。
現代の物理学では、宇宙には重力、電磁気力、強い力、弱い力という四種類の力があるとされ、それぞれについて理論がある。たとえば相対性理論は重力を説明する理論であり、強い力と弱い力にはそれぞれの量子論の理論がある。ところが四つの力すべてを説明できる統一理論が未だ発見されていないのである。そのためそういうものが発見されるまでは、ビッグバンのプロセスの様なこの四つの世界すべてに関わるであろう物理現象は完全解明できない。
その様な統一理論は、物理世界のすべてを説明できると期待され、そのため「万物の理論」Theory of Everything と呼ばれ、M理論という候補などが研究されている。しかし、重力を除く三つの力を統一する「大統一理論」Grand Unified Theory でさえ未完成なのである。ちなみに、万物の理論は「超統一理論」と呼ばれることがある。いずにせよ、我々が日々使うスマホやGPSなどを生み出す大発展を遂げまた発展しつづけている物理学には、その全体を説明できる統一された基礎「万物の理論」が未だにないのである。
しかし、数学では、既にそういう「万物の理論」、それひとつで数学の理論のすべてを展開できる ZFC や TG という理論が存在しているのである。この ZFC と TG はともに公理的集合論と呼ばれるもので、要するには高校でも学習する集合についての理論である。集合論に「公理的」という形容詞が付いているが、これはこの理論が、「二つ集合 \(A, B\) に対して、その和集合 \(A∪B\) が必ず存在する」や「二つの集合が同一なのはそれが同じ要素を持つ時だ」などの集合についての公理のリストでできているからである。つまり、これらは集合の基本性質を少ない数の公理にまとめたものなのである。
そして、これが「数学の万物の理論」であるということは、数学において証明を行うということは、これらの公理から論理だけを用いて証明することだということを意味する。先に ZFC や TG は、それらで数学における証明が実行できるだけでなく、自然数や複素数など、どの様な数学的対象が存在するかが規定されていると書いたが、これは ZFC や TG の公理がその存在を保証する集合として数学的対象を定義することを意味している。
たとえば自然数の \(0\) (ゼロ)は空集合 \(\emptyset\) として定義する。そして、ある自然数 \(a\) が集合 \(A\) として定義されたとき、\(a+1\) にあたるものを和集合 \(A\cup\{A\}\) として定義する。そして、 ZFC の公理を使うと、\(\{0, 0+1, 0+1+1,\ldots\}\) という集合、つまり自然数の集合 \(\{0, 1, 2,\ldots\}\) にあたる集合の存在を証明できるので、この存在の証明をもって自然数の集合が定義されたとする。現代の数学における数学的対象の定義は、こんな風なやり方で行うのである。これは非常にエレメンタリーなレベルの定義だったが、それがどんなに複雑高度なものあっても、同じようなやり方で現代の数学において存在するとされるものは、すべて ZFC や TG という理論を使って集合として定義・構築可能なのである。
自然数のゼロを空集合とし \(a+1\) を \(A\cup\{A\}\) で定義することは現代数学の自然数の定義の標準だが、これは何か必然的な理由があるからそう定義するわけではない。単にこうすると便利だというだけのことだ。現代数学ではある存在が「何でできているか」ということには意味がないと考え、それが他の存在とどういう関係にあるかということだけを問題にする。自然数でいえばゼロという存在があり、ある自然数 \(a\) にはかならず次の数 \(a+1\) があって、ゼロは \(a+1\) にはならないとか、\(a+1=b+1\) ならば \(a=b\) だとかの「ペアノの公理」と呼ばれる5つの条件さえ成り立っていれば、どんなもので出来ていても自然数と認める。そういう見地からは上に説明した自然数の定義が簡単で便利なのである。西洋の伝統的考え方では、存在が何でできているかという「実体」の問題を重視するが、これはそれと対極をなす「モダンな考え方」である。ちなみにマックス・ヴェーバー系の社会学では社会の中の存在を役割(ロール)で考え、その役割を果たす人が誰であるかを無視するが、これも同じモダンな考え方だ。
数学における定義や証明は、 ZFC や TG の少数の公理から論理だけを用いて数学的対象を定義して、その性質を定理として証明することだというのが数学という学問の公式見解となっている。つまり、 ZFC や TG により数学という活動の基本のすべてが準備されているといえる。数学の理論を展開するとは、これらの公理的集合論の公理から論理だけを使って推論することなのである。その意味でこれらは「数学の万物の理論」なのである。
その「数学の万物の理論」の第一バージョンである ZFC は1920年代に誕生した。そして、それが代数幾何学という分野で必要となったグロタンディエク・ユニバースというもので拡張されて、現在の標準的数学版万物の理論である TG が生まれたのは1960年代のことである。 TG の G は、このグロタンディエク・ユニバースを使い始めた数学者グロタンディエク Grothendieck の G であるが、 TG の T である数学者タルスキ Tarski が、シェルピンスキとの共著論文で理論的にはグロタンディエク・ユニバースと同じものである到達不可能基数を提案したのは1930年のことだった。
ZFC が提唱されたころ、まだ、代数や幾何学などの分野は到達不可能基数を必要としなかったが、数学の発展による必要性から、1960年代に ZFC がグロタンディエク・ユニバースという形の到達不可能基数で拡張され現在の数学の標準的万物の理論 TG になったのである。ちなみにグロタンディエク・ユニバースを必要としない数学の分野も多く、それらの分野ではいまだに ZFC が万物の理論の標準である。
この様に「数学の万物の理論」はすでに1930年に存在していたと言ってよい。そして、その約90年後のこの文章を書いている2020年代まで、数学における証明は「数学の万物の理論」である公理的集合論 ZFC と TG の公理からの論理推論で完全にカバーされているのである。これは他の学問と比較してみると驚くべきことだということがわかる。
もし、自然科学のある分野の基礎理論が1930年代から全く変わっていないとしたら、それはその分野が停滞している、あるいは、もう終わってしまっていることを意味するだろう。この一世紀ほどの自然科学の目覚ましい進歩を振り返れば、ほとんどの分野は、その基礎理論を根本的に書き変えることによって進歩していることがわかる。生命科学では1950年代に分子生物学が誕生して、生命というものについての見方ががらりと変わった。化学も量子力学などの物理学との合流により、その姿を大きく変えた。その物理学はそれまでに知られていた重力・電磁力に加えて、強い力・弱い力という新しい力を発見し、それら四つの力を統一する真の基礎理論「物理学の万物の理論」に向けて邁進している。
ところが数学だけは基礎理論が1930年から実質的に変わってないのである。数学者たちのほとんどは1930年代には実質的に存在していた TG、また分野によっては ZFC で十分と考えていて、それを利用するものの、それを変えようなどとは考えない。最近、集合論の代わりに圏論というものを使うことが増えているが、これも結局は TG の使い方のひとつのスタイルで、基礎付けということでいえば TG と変わらない。つまり、 ZFC や TG は数学者のニーズからすると完成され、それ以上何かする必要がないものなのである。
集合というもの自身に興味をもつ数学者は存在し、 ZFC や TG 自身の数学的性質の研究を精力的に続けている人たちが相当数存在し優れた成果が得られているのも事実であるが、その数は多種多様な分野がある数学に従事する数学者全体の数からみれば少ない。また、これらの集合論研究者も集合が数学的対象として興味深いから研究しているのであって、数学の基礎付けが必要だから集合論を研究をしているのではない。これらの集合論研究者のほとんども「数学を行うための基礎としての集合論」は実質完成していると思っている。
特筆すべきことは、物理学、化学、生物学などの自然科学の諸分野と違い、これは数学が1930年以後停滞していることを意味しないことである。それどころか1930年代以後、現在までの数学の進化は人類の歴史上経験されたことがないほど爆発的なものであった。フェルマー予想、ポアンカレ予想、次々と未解決問題が解決され、それらを遥かに超えた大きな目標に向かって数学は今日も発展し続けている。変わらないのはその基礎だけなのである。
この「基礎の停滞」は、むしろ「基礎の安定」として数学の大発展を支えている。数学者たちは自分たちの足元が揺らぐことを心配することなく、安定した基礎の上で高度な数学理論を自由にのびのびと開拓できるからである。そして、こういう状況は、これから先の長い期間変わらないだろうと信じられている。つまり、数学をするに必要な証明と定義のための方法は、すでに1930年に完成され、これからもそれは揺らがないと思われているのである。こういう意味で、 ZFC と TG は、まさに「数学の万物の理論」と呼んで良いものであるし、その様なものが1世紀近くも前に発明されたということは、他の諸学と比較する時、「イデアの学である」という数学という学問の特異性に基づく驚くべき出来事だったといえるのである。
3. 数学の万物の理論は不完全

この様に、1930年には ZFC , NBG(の初期バージョン)という「数学の万物の理論」が既に存在し、現代の「万物の理論」である TG さえも実質的に存在していた。ところがである。その翌年の1931年、オーストリア共和国ウィーン大学の新進数学者クルト・ゲーデル Kurt Gödel が衝撃的な定理を発表した。当時の「数学の万物の理論」であった ZFC , NBG、 そして、 TG のように、それらに有限個の公理を追加した理論はみんな不完全だというのである。これを「ゲーデルの不完全性定理」という。
正確に言うとゲーデルが証明したことは、 ZFC の部分体系とみなせる PM という歴史上最初の「数学の万物の理論」が、\(\,\omega\)-無矛盾という条件を満たすならば不完全である、と言う事実だった。しかしゲーデルが注意した様に、その証明が ZFC や NBG、さらにはそれらに有限個の公理を追加した TG の様な理論についても適用できることは明瞭だったのである。
ここで「ある理論が不完全」とは、その理論の言語で記述できる命題で、それも、その否定もどちらも証明できないものが存在することを言う。その様な命題を専門用語で「形式的に決定不可能な命題」と言う。1931年の不完全性定理論文でゲーデルが最初の形式的に決定不可能な命題を作って見せて以来、様々な進歩があり、現在では、古代以来数学の最も基本的な研究対象の一つであったディオファントス方程式の解の存在についての命題の中に、形式的に決定不可能なものがあることがわかっている。つまり、「\(p(x_1,\ldots,x_n)=0\) となる整数 \(x_1,\ldots,x_n\) は存在しない」という命題が形式的に決定不可能になるような整数係数の方程式 \(p(x_1,\ldots,x_n)=0\) が存在するのである。これは「\(p(x_1,\ldots,x_n)=0\) となる整数 \(x_1,\ldots,x_n\) は存在しない」という簡単至極の数学的問題の中に、「数学の万物の理論」をもってしても解決できないものがあるということである。
上で「命題」という言葉を使ったが、これは高校の数学で学ぶ言葉で、真(正しい)か偽(正しくない)かが確定するような主張のことである。しかし、真なのか偽なのかはわかってなくてもよい。たとえば上に書いたディオファントス方程式についての主張は「数学の万物の理論」で、それ自身もその否定も証明ができなくても、命題であることに変わりはない。一方で式 \(x^2=4\) は命題ではない。これは \(x\) の値が確定してないので式の真偽が確定しないからである。
不完全性定理には「理論が\(\,\omega\)-無矛盾である」というテクニカルな条件がついていたが、これを「理論が無矛盾である」、つまり対象となる理論が矛盾しないこと、つまり、どの命題をとっても、それとその否定が同時に証明できることはないという条件に弱められることが、数年後に判った。また、ゲーデルの1931年の証明でも「理論が無矛盾である」という条件だけで「正しいと分かるのだが、それが証明できない命題がある」ということは示せた。そして、その命題を \(G\) と書くとすると、\(\,\omega\)-無矛盾という条件を追加するならば、この \(G\) の否定も ZFC で証明することができないということをゲーデルは示したのである。これをゲーデルの第一不完全性定理という。「第一」が付いているのは第二不完全性定理というものがあるからだが、それは第10節で説明することにして、話を続ける。
理論が無矛盾であるという前提がついているが、矛盾した理論はもともと意味が無いし、数学者たちは「数学の万物の理論」は無矛盾だと信じている。それを信じられないようならば、こういう理論を使う気にはなれないだろう。非常にまれな例外はあるが、数学者たちは「数学の万物の理論」は無矛盾であるだけでなく「正しい」と信じている。つまり、第一不完全性定理は「命題 \(G\) を数学者は正しいと信じているが、数学者が日々使う数学の理論では \(G\) は証明できない」、そういう命題 \(G\) が存在することを示していたのである。
この様に書くと数学者たちの間に大きな衝撃が走ったのではないかと思うかもしれない。実際、この定理に非常に大きな衝撃を受けた数学者、それも当時の数学の世界を代表する大数学者ドイツのダーヴィット・ヒルベルト David Hilbert や、将来の大数学者として期待されていたフランスの若きジャック・エルブラン Jacques Herbrand の様な人たちはいた(これについては???で説明する予定)。しかし、彼らは少数派であり、大多数の数学者にとっては、これはそれほど大きな衝撃ではなかったのである。そして、現代にいたっては、数学者の殆どは、こういう問題に興味を示さない。
それはなぜなのか。それが本サイトのテーマである「数学の近代化」ということであり、その意味を説明するには幾つか背景知識も必要なので、その説明は後回しにして、第一不完全性定理の証明の仕組みなどのより入門的な話を続ける。まずは、1931年のゲーデルの第一不完全性定理をもっと正確に定式化する。そのために次の第4節で記号論理学の話をし、今まで説明してきた「不完全」とか「\(\omega\)-無矛盾」をより正確に説明するが、これらは簡単な話ではなく記号も相当使う。そこで、この節が理解できなくても、第5節は一応はわかるように書く努力をしたので、次節の第4節は敬遠して直接第5節を読んでもおそらく読めると思う。
4. 不完全性定理のための記号論理学(少し advanced)
この節は少し advanced で記号も多く使う。この様なことをするのは、\(\omega\)-無矛盾という1931年の不完全性定理の前提条件を或る程度の正確さを持って説明するためである。しかし、すでに注意した様に、ゲーデルの発見の数年後には、この条件を普通の無矛盾性に置き換えても不完全性定理はなりたつことが発見された。そのため、\(\omega\)-無矛盾という条件や、その様な条件のもとで不完全性定理を考えることは、現在では過去のものとなっているといってよい。その様な次第で、1931年のゲーデルのオリジナルな不完全性定理の形を知ることに拘らないのならば、この節は飛ばして次節を直接読んでも次節以後の話は理解できるはずである。では、説明を始めよう。
TG, ZFC, NBG, PM などの今まで出てきた「数学の万物の理論」は、すべて記号論理学という数学の一分野の方法で記述されており、特に ZFC, TG の場合には「集合に関する一階述語論理」というものが使われている。これら二つの理論を、「集合に関する一階述語論理」で記述するとは、\(a, b, A, B\) などの変数、等号 \(=\)、要素の記号 \(\in \)、左右の括弧 \(( )\)、変数を区切る時に使うコンマ、そして、論理記号とよばれる \(\exists , \forall , \lor , \land , \Rightarrow , \Leftrightarrow , \lnot \) などの記号の有限列である論理式というもので、これらの理論の命題を記述し、そしてこれらの理論の証明は論理式の列として記述するということである。そして、ZFC, TG などの「数学の万物の理論」とは、そういう論理式としての命題で記述した「集合についての公理の有限個のリスト」なのである。
ZFC, TG で、二つの集合 \(A, B\) に対して、その和集合 \(A\cup B\) が存在するという公理は、\(\forall A\forall B\,\exists C\,\forall X((X\in A\lor X\in B)\Leftrightarrow X\in C)\) という論理式となる。変数 \(A, B, C, X\) は集合を表し、\(\forall, \exists, \lor , \Leftrightarrow\) は、それぞれ「任意の…に対し…」「ある…が存在して…」「または」「両辺が同値である」を表すので、これは「すべての集合 \(A, B\) に対し、ある集合 \(C\) が存在して、任意の集合 \(X\) に対し、「\(X\in A\) または \(X\in B\)」は \(X\in C\) と同値となる」を意味する。つまり、この公理が存在を保証する集合 \(C\) がふたつの集合 \(A\) と \(B\) の和集合なのである。
ちなみに、\(A, B\) の要素となる \(X\) として集合しか考えていないが、ZFC, NBG, TG ではすべての集合は要素として集合しか持たず、集合というものは全部、空集合 \(\emptyset\) を出発点とし、次にそれを要素にする \(\{\emptyset\}\) を作り、その次に \(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\) を作り…という風に作られると考えるからである。そういう風な集合しか考えないことにした理論は NBG が最初で、その考え方が後に ZFC でも採用された。また、先に紹介した自然数の定義も NBG 由来で、\(0, 0+1, 0+1+1,\ldots\) と定義される自然数が、\(\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\},\ldots\) になっていて、同じ考え方だとわかる。
一階述語論理は論理式の間の推論の関係を定義していて、それにより公理からどういう論理式が証明できるかを規定する。つまり、「数学の万物の理論」である ZFC や TG の公理から、どういう論理式が証明できるかが一階述語論理というもので規定されることにより、「数学における正しい証明」というものが規定(定義)されているのである。一階述語論理は数学の一分野の方法で、それは代数や解析での数式の導出の方法と似た方法で記述される。つまり、数学における証明というものが数学的に定義されているのである。
論理式というものは「数学で使われる式」という意味での数式の一種だが、論理的な表現を行う式である。例えば \(a=b\) が論理式で、その否定の論理式が \(\lnot a=b\) である(これは \(a\neq b\) と同じ意味である)。こういう変数を含んだ式を考えるときには、\(a, b\) の値がコンテキストで決まっているとするか、どんな \(a, b\) に対してもその数式がなりたつと考えるわけだが、それは論理式の場合も同様である。そのため変数を含む論理式の「否定」を考えるときには注意が必要となる。
たとえば、ZFC, TG 等の理論で集合和 \(A\cup B\) を定義して、それの交換法則を論理式で書くと \(A\cup B=B\cup A\) となる。これは当然ながら ZFC, TG で証明できるのだが、これの否定の論理式 \(\lnot A\cup B=B\cup A\) の意味は「どんな二つの集合 \(A, B\) に対しても \(A\cup B\neq B\cup A\) となる」になってしまう。しかし、\(A\cup B=B\cup A\) の意味である「どんな二つの集合 \(A, B\) に対しても \(A\cup B= B\cup A\) である」の否定は、「\(A\cup B= B\cup A\)とならない集合 \(A, B\) もある」だから、論理式に否定の記号 \(\lnot\) をつけただけでは、その論理式の意味を正しく否定したことにならないことがわかる。
こういうことがあるので論理式では、「どんな」とか「すべての」という風に言う時には、論理記号 \(\forall\) を使って明示する。たとえば集合輪の交換法則は \(\forall A\) と \(\forall B\) を前につけて \(\forall A\forall B(A\cup B=B\cup A)\)と書くと「どんな二つの集合 \(A, B\) に対しても \(A\cup B=B\cup A\)」を表すことになる。そうすると否定の記号 \(\lnot\) を前につけた \(\lnot \forall A\forall B(A\cup B=B\cup A)\) は、意図通り元の論理式の否定になる。
論理式 \(\forall A\forall B(A\cup B=B\cup A)\) のように \(\lnot\) を前につけただけで正確に内容が否定される様な論理式を閉論理式という。高校の数学の集合と論理で「真か偽であることを判定できる主張」である「命題」というものを学ぶが、これがそれである。つまり、記号論理学では「命題」とは閉論理式のことなのである。ただし、専門用語では「命題」といわず、「文」sentence ということも多い。一方、閉論理式でない \(A\cup B=B\cup A\) の様な式は開論理式という。変数 \(A, B\) の値が未定で「開いている」という感じである。開論理式、閉論理式は、こういう「開いた変数」が有るか無いかで定義するのだが、正確な定義は中級編で行う。
さてこれで準備ができたので、 ZFC や TG のような記号論理学の理論が「無矛盾」「完全」であるとはどういうことか定義しよう。
数学では矛盾する理論は意味をなさないとされ無矛盾な理論のみが使われる。たとえば ZFC や TG は無矛盾だと信じられている。また、これらの理論が完全であるならば、それは理論で記述できる数学の問題(命題、閉論理式)の真偽をその理論のみで判別できることを意味している。
ちなみに無矛盾性の方は閉論理式だけでなく論理式一般を使って「どの様な論理式 \(F\) に対しても、決して \(F\) と \(\lnot F\) が同時に証明されることはない」と定義されることが多い。これは普通の理論では、この定義と \(F\) を閉論理式に限定した定義が同値だからである。しかし、完全性の方で閉論理式を一般の論理式に変えたものは完全性と一致しないので、ここでは完全性の定義と無矛盾性の定義の形をそろえるために上の様に定義した。
さて、この節の最後にゲーデルが使った「\(\omega\)-無矛盾性」というものを定義しよう。
これで準備は整ったので、次に第一不完全性定理を正確に述べよう。
5. 第一不完全性定理
1931年にゲーデルが証明した第一不完全性定理とは、次のような定理である。
「この命題はこの理論の証明方法では証明できない」と説明したゲーデル式 \(G\) は自己参照文と呼ばれるものの一種で、書き変えると次の様になる。
また、ゲーデル式の等式の右辺の「この理論」というのは、第一不完全性定理の考察対象の TG, ZFC, NBG, PM などの理論のことだ。ゲーデル式 \(G\) といったが、それはこれらの理論を一つ固定したときに定義されるものなので理論の数だけゲーデル式はある。つまり、正確を期すならば、\(G\) は理論ごとに \(G_\textsf{TG}, G_\textsf{ZFC}, G_\textsf{NBG}, G_\textsf{PM}\)などと書くべきものである。そして、たとえば、TG で形式的に決定不可能になる命題は、 \(G_\textsf{TG}\)であって、\(G_\textsf{ZFC}, G_\textsf{NBG}, G_\textsf{PM}\)ではない。実際、これら三つは TG で証明できる。
定理の条件である、\(\omega\)-無矛盾性は、前節で説明したようにかなり複雑で初学者には理解し難い条件である。詳しく知りたいならば前節を見て欲しいが、要するには理論の無矛盾性、つまり「どんな命題 \(P\) にたいしても、\(P\) とその否定 \(\lnot P\) の両方が証明されることはない」という条件を強くした条件になっている。つまり、ある理論が\(\,\omega\)-無矛盾ならばそれは無矛盾である。ゲーデルが上の様な形で第一不完全性定理を発表した5年後、アメリカの数学者ロッサ―がゲーデル式をわずかに変形すると、\(\omega\)-無矛盾性を無矛盾性に変えても定理が成り立つことを発表した。そして、現在では、第一不完全性定理は、このロッサ―のバージョンで述べられることが多い。つまり、次の様に述べられる。
また、既に述べたように、ゲーデルの1931年のゲーデル式と不完全性定理の証明でも、次のことは示されていた。
しかし、これは\(\,\omega\)-無矛盾性が全く意味を持たないというわけではない。実は、中級編で示すように、TG, ZFC などが\(\,\omega\)-無矛盾かつ完全であると仮定すると、自然数についてだけ語る命題では、正しいことと、その理論で証明できることが同値になる。そして、この数学的事実を、ある歴史資料と合わせると、ゲーデルが第一不完全性定理を発見した経路を推測できるのである。これについては中級編で説明する。
「\(\omega\)-無矛盾ならば \(\lnot G\) も証明できない」の証明は、\(\omega\)-無矛盾性の定義がわかっていれば難しくはない。しかし、これの定義は飛ばして読んでもよいことにしているし、先に説明した様に「\(\omega\)-無矛盾ならば \(\lnot G\) も証明できない」の方は、ある意味で「おまけ」なのだから、次節では第一不完全性定理のエッセンスというべき「無矛盾ならばゲーデル式は真だが、それは当該理論では証明できない」の証明だけを説明する。もう一方の証明は、中級編で行う。
さて予め言っておくべきことは全て言ったので第一不完全性定理の証明の解説に移ろう。解説は次からの三つの節で行う。
6. 不完全性定理証明のカラクリ1:「万物の理論」の自己参照
第一不完全性定理の証明には、前節で説明したゲーデル式の自己参照性が本質的に関わっている。そして、ゲーデル式の様な自己参照的命題が作られる理由は、それらの理論では、自分自身の中に自己参照的に「自分自身のモデル」を作ることができるからなのである。次節で説明するゲーデル数というものを使ってそういう自己参照的「モデル」を作って見せたことが、ゲーデルの1931年の論文の最大の数学的アチーブメントであったといえる。そして、そういうことが可能なのは、ZFC, TG などが「万物の理論」であるからなのである。ある意味で「万物の理論」に不完全性が生じるのは、それが「万物の理論」だからなのである。
この様に不完全定理を「万物の理論」と関連づけるのは、ブラックホール理論で有名な物理学者スティーブン・ホーキングが「ゲーデルと物理学の終」という講演で行ったことである。ホーキングは、物理学者ディラックの生誕100年を祝うために2002年7月20日に行ったこの講演で、ある理由で「物理学の万物の理論」にも「数学の万物の理論」のように決定できない命題があるのではないかと議論し、その主張の意味をゲーデルの不完全性定理とのアナロジーで語ったのである。以下の解説は、ホーキングの「物理学の万物の理論の不完全性の可能性」についての主張をSF的シナリオを使ってわかり易くし、逆に、それとのアナロジーを使って、「数学の万物の理論」の「万物の理論性」がゲーデル式を生み出すカラクリを説明したものである。
ちなみに、本稿では「数学の万物の理論」とは、必要な数学の定義と証明が実質的にできて、それだけで良いと数学者が満足している理論のこととしているが、ホーキングはこういう現実的な立場ではなく理想的立場を採り「物理学の万物の理論」は、前節、前々節で定義した意味で完全な理論でないといけないとした。そのため、彼は自分の議論を「物理学の万物の理論は不完全かもしれない」という議論ではなく「物理学の万物の理論は不可能かもしれない」という議論として説明している。この同じ言葉の異なる二つの使い方に注意して以下の解説を読んで頂きたい。
ホーキングの講演の題名の「物理学の終」とは、物理学が進歩して物理現象のすべてを説明できる「万物の理論」が完成すれば、それは物理学が終着点にたどりついたことであり、研究分野として終わってしまうだろうということであった。ホーキングにはポピュラーサイエンスの大ベストセラー「ホーキング、宇宙を語る」があるが、彼は1988年に出版されたこの著書では、物理学の究極の目標は「物理学の万物の理論」だと書いている。しかし、2002年の講演では、最初はそう信じて、また、その目標の達成の可能性も信じていたが、今では考えが変ったと語った。ゲーデルの定理の様に「物理学の万物の理論」には、それでは説明できない現象が常に残り、それはネガティブなことではなくて、むしろ物理学が終わらないというポジティブなことだろうと考えるようになったと彼は語ったのである。
不完全性をポジティブに取るホーキングの考え方は、「数学の万物の理論」と第一不完全性定理の関係としてゲーデルが主張したことで有名である。不完全性定理は「理性の限界」「数学の限界」を示すものととして語られ勝ちなのだが、ゲーデル自身はそれと正反対の立場を採り人類の数学知に限界はないと考えた。限界があるのは ZFC, TG のような「形式的な体系」であり、人知の可能性はそれを超えて幾らでも開かれている。必要とあらば人類は「万物の理論」を正しく拡張して、どんな数学の問題でも正しく解決することができる、第一不完全性定理は、そういう意味で人類の知が無限に開かれていることを示す定理だと主張したのである。「ホーキング、宇宙を語る」ではゲーデルや不完全性定理への言及はないが、不完全性定理と「数学の万物の理論」による数学の基礎付けの歴史的経緯などを意識して書いたのではないかと思える文章が幾つもある。ところでホーキングが不完全性定理を根拠に「物理学の万物の理論の不可能性」を主張したという意見があるが、私が知る限り、ホーキングがそういう議論をしたことはない[注1]。
ホーキングは「物理学者も万物の一つなのだから、万物の理論の法則により、物理学者が万物の理論に到達できないと決まっていてもおかしくない」と主張した。この主張の「万物の理論の法則により、物理学者が万物の理論に到達できない」という部分は、どういう仕組みでそうなのか説明されてないので、分かりにくいのだが、次の様に考えると確かに起きても不思議はないと思えてくる。
ホーキングは「物理学の万物の理論」とは、「有限個の概念と法則で記述された理論で、それにより物理現象のすべてが説明できる理論」をいうとした。もし、そういうものがあるとしたら、そういう法則をコンピュータ上にプログラムできれば、本当の宇宙を完全にコピーした「宇宙モデル」ができるだろう。さらに大胆にSF的に考えれば例えば次の様なシナリオも考えられる。
実は、我々のこの世界は、ある物理学者が作り出したコンピュータ・モデルであり、この世界の物理現象もすべてその人物が決めてプログラムしたものである。つまり宇宙創造の神はひとりの物理学者なのである。そして、「神」は、そのことを我々に悟られない様に人類の知能にある種のブレーキを仕込んだ。つまり、我々人類の知能にはもともと限界が設けられている。そのため、宇宙のすべての事象を説明できる理論に我々人類が到達することは不可能である。
ホーキングがこういうSF的状況を考えていたとは思えないが、こういう「人工宇宙」でなくとも、宇宙が持つ何かの法則がその中に棲む知的生物の知性に一定の限界が生まれるブレーキの役目を果たす可能性は、論理的には排除できない。だからホーキングが主張したようなことが起きても少なくとも論理的には不思議はないのである。
そして、「数学の万物の理論」の場合には、このSF的「人工宇宙」の状況が実際に起きていると考えられるのである。そして、それがこの節の最初の段落で説明したことなのである。この様に考えるには、科学的事実だけでなく、数学という行為の社会学的分析も必要となる。以下でこれを説明しよう。
「物理学の万物の理論」は、まだ研究中であり存在していない。物理学者は宇宙という物理世界は「そこに」存在していて、自分たちは、それを観測し理論づけて記述していると考える。その記述するものが相対性理論、量子力学などの物理学の理論であり、それの究極のものが「物理学の万物の理論」である。「物理学の万物の理論」は、まだ存在しないものの「物理世界」「宇宙」という「実体」は存在すると信じられているから、その「実体」を語る「理論」、宇宙を語る完全な言葉について語れるのである。
一方で、数学の場合には、「数学の万物の理論」がすでに存在している。数学者は「数学世界」について語る十分な理論、言葉を獲得しているのである。では、一方で「実体」の方はどうか?数学の対象、数とか集合とか、そういうものは実在するのだろうか。
物理ならば私たちは目の前のタブレットやスマホ、PCを触ったり見たりして、その存在を「実感」できる。ニュートン力学のレベルならば、簡単に実験をしてその力学法則を実感することさえできる。GPS衛星を作るエンジニアならば、計測移置の大きなずれとして一般相対性理論が予測する衛星軌道における重力の低下による時計の進みを実感できる。しかし、誰か数字の1でなくて、この1と言う文字が表す数の1そのものを見た人はいるだろうか。それに触ったことがある人はいるだろうか。我々は生得的感覚によっては、1の「実体」を実感できない。
アンケートをとって調べたわけではないので、あくまで元数学者である私個人の経験からくる意見であるが、多くの数学者は自分たちが研究している数学対象が実在していると考えていると思う。数学者の大半は、その研究対象がいかに抽象的なものであろうと、日常的に接する「もの」と同じようにその数学的対象に接している。
とはいいながら、数学の場合は物理学の場合と異なり、そういう対象は数学者各自の思考の中にしかない。たとえば、二人の数学者が実数について相反する定理を主張し、それがそれぞれの数学者が主張する実数の基本的原理の差から来ているとしよう。しかも、それぞれの基本原理や主張には自己矛盾はないとする。どうやってどちらが正しいと判断できるだろうか。
こういう場合、物理ではどうすれば良いかはっきりしている。実験である。量子力学の基本原理に納得がいかなかったアインシュタインが、量子力学を否定しようとして考えたEPRパラドックスは、こういう状況の典型である。しかし、既に書いたように、アインシュタインの哲学的な原理には反していたEPRパラドックスの現象は、実際に起きることが色々な実験で示されるようになり、その現象が現在では量子暗号に利用される様になっている。物理の場合は、この様に物理学者が共有する「物理的存在」がある。しかし、数学の場合はそういうものがないのである。
もしそういう数学者の社会で、数学者間の思考の世界にズレがあったら、数学者たちは互いにその定義や証明をコミュニケートすることさえできなくなる。先に書いた実数についての相反する定理のようなことが起きたら、判定基準がないのである。数学で、そんなことが起きるわけはないと思うかもしれないが、19世紀の終ごろから1930年代にかけて、数学の基礎がゆらぎ証明や定義に関する基本原理が定まらず、遂には不連続な実数関数は存在できないようなオールタナティブな数学「直観主義数学」というものまで提案された。しかも、このオールタナティブな数学は無矛盾だったのである。つまり、数学者により「数学的な正しさの基準」が異なり、なにが数学的真理かが揺らいだ時代が実際にあったのである。これについては「???数学基礎論の時代」を参照してもらうことにして、ここでは説明を省略する。
幸いなことに1930年代ころから ZFC が数学の基礎として広く認められるようになり、第2次世界大戦が終り1950年代に入るころには数学の標準的基礎として定着した。そして、その後グロタンディエクの代数幾何学理論のために ZFC が TG に拡張され、これが数学の基礎の標準になっているわけである。そのため数学者間で思考を共有するには最終的にはZFC, TG などの「数学の万物の理論」に戻って、自分たちの定義や証明を、これらの理論の集合の言葉で記述して論文などとして発表することになっている。そして、論文の内容がZFC, TG などの理論の規則に従って記述されていると判定できたときに、その論文の結果は正しいとされて専門誌に掲載される。そして、それは正しい事実として数学者集団に受け入れられるのである。
この様に考えれば、数学者たちの集団が行う社会的行動としての「数学」は、ZFC, TG などの「人工言語」に従うアイデアの交換となる。アイデアを交換するには、自分の思考の世界の中のイデア的存在を駆使した数学的考察を、一旦、人工言語であるZFC, TG などの言葉で記述しないといけない。実は、これはプログラム言語を使ってプログラムをしている行為に非常に近いのである。実際、ZFC, TG などの理論は形式理論と呼ばれるもので、プログラム言語やWEBページを記述(コード)するために使われるHTMLやCSSと同様に形式言語と呼ばれるものの一種なのである。次の「こぼれ話」の「証明のコーディングと現実の証明」で説明するように、現実の証明はプログラムとはほど遠いものだが、公式には、それはプログラムの様なものに翻訳してZFC, TG で証明できなくてはいけないとされているのである。
TG という名称は、タルスキとグロタンディエクという二人の数学者の名前から来ていた。 ZFC もNBGも、 ZFC のCが選出公理 Axiom of Choice の C である以外は、みな、それらを作った数学者たちツェルメロ Zermelo、フレンケル Fraenkel などの名前の頭文字である。つまり、「数学の万物の理論」という「数学の定義と証明の宇宙」は、これらの数学者たちによりプログラムされた「人工宇宙」の様なものだと考えることができる。そこでこのアナロジーを使って、不完全性定理を証明するために、ゲーデルが行ったことを説明しよう。
さきほど「物理学の万物の理論」の可能性についてのホーキングの「懸念」あるいはそれを180度転回した「希望」の理由づけをわかり易くするために、この宇宙がある物理学者が作り出した人工宇宙だと仮定してみた。その時には、ホーキングの考えをわかり易くするために、その物理学者がプログラムに細工をして、人工宇宙内の人類が「万物の理論」にたどり着けないようにしていると考えた。しかし、その反対を考えることもできる。つまり、人工宇宙の中の物理学者が、自分が棲む宇宙の「万物の理論」を発見できるようにプログラムされていると考えることもできる。もし、そうならば人工宇宙の中の物理学者は、自分の発見した理論を使って、自分自身の人工宇宙をプログラムできるだろう。そして、そういう風にできた人工宇宙は同じ法則に従っているので、自分が棲む人工宇宙と瓜二つのはずである。つまり、人工宇宙1の中に、それのコピーである人工宇宙2が存在して、この二つが全く同じ構造をしているのである。
これは宇宙モデルの自己参照であるが、ゲーデルは不完全性定理を証明するために、この自己参照の状況がTG, ZFC, NBG, PMなどの「数学の万物の理論」では実際に起きることを証明した。つまり、これらの理論の中に、それら自身の瓜二つのコピーが作れることをしめしたのである。そして、それを使って例えば TG の命題として「この命題は TG では証明できない」あるいは別表限で「\(G_\textsf{TG}=\)「\(G_\textsf{TG}\) は TG では証明できない」」というゲーデル式 \(G_\textsf{TG}\)を作ってみせたのである。そして、そのために使ったのが、次節で説明するゲーデル数という有名なテクニックだった。
数学の証明は ZFC や TG の証明に翻訳できて初めて正しいとされる。これは殆どすべての数学者が認める「公式見解」である。例えば数学者が物理学者に、どうしてあなたの定理は正しいといえるのか、実験で検証できるわけでもないのにと問い詰められた場合、「TG や ZFC の証明に翻訳できるからだ」と答えることになる。応用数学は別だが純粋数学だと、面倒な哲学的議論をしないで済ませるには、これ位しか返事が考えられないのである。しかし、現実に数学者が書いた証明を形式言語に翻訳するのは大変な作業で、たとえば紙の上でそれを行うことは短い証明でもほとんど不可能に近い。形式言語で証明を書くと、物凄く長くなるからである。そのため、「証明のコーディング」を補助するアプリが色々作られている。例えば TG 用としては Mizar が有名で、多くの定理が証明されている。しかし、膨大な数学の定理の数から考えれば実際に証明された定理の数は非常に少数だし、アプリの助けを得ても形式言語で証明することは大変である。そのため第一不完全性定理とか四色問題などの有名な定理が、Mizar の様なアプリで証明されると、それだけで論文になる。そんな風なので、ほとんどの数学者は「証明のコーディング」には興味を示さず、「原理的にはコーディングできる」という所までしかチェックしない。というより、そのようにチェックされるのも極めてまれなことで、 ZFC や TG の公理さえ知らない数学者も多い。それでも共有され継承される文化としての数学の「正しさ」は十分に保たれている。
7. 不完全性定理証明のカラクリ2:ゲーデル数
ゲーデルは「数学の万物の理論」の中に、その理論自身のコピーを作るためにゲーデル数というものを使った。「数学の万物の理論」の一つの中に、それ自身のコピーを作るとは、この理論、例えば TG の命題、証明などにあたるものを TG の中に作り、そして、「\(x\) は命題である」とか「\(x\) は証明可能な命題である」などの性質を TG を使って記述することを言う。その記述には、第4節でも紹介した \[ \forall A\forall B\exists C\,\forall X((X\in A\lor X\in B)\Leftrightarrow X\in C) \] がその一例である論理式というものを使うが、要するにはこの例のような文字列である。ただし、ここで「文字列」と言っているのは、IT用語の文字列のことで、文字列の「文字」には括弧や等式のような数学の記号なども含まれるとする。
\(\forall\) は顔文字に使われることが多い文字だが、もともとは \(\forall a\cdots\) と書いて「すべての \(a\) について \(\cdots\) が正しい」という意味の論理式を作るための記号で論理記号と呼ばれる。\(\exists , \lor , \Leftrightarrow\) も同様に論理記号だが、その具体的意味は第4節を見てもらうことにして、ここでは説明を省く。ゲーデルは、こういう文字列をゲーデル数と呼ばれる自然数で表した。
自然数で文字列を表現するゲーデル数の方法は簡単で素因数分解を使う。まず理論で使用する文字のすべてに適当に自然数を割り振っておく。以下では、この割り振った自然数を「文字の番号」と呼ぶ。現代的に言えば、これは文字のコードである。この番号付け、コードを元に、ある文字列のゲーデル番号を計算するには、まず、最初の素数2から、文字列の長さと同じ数だけの素数を用意する。そして、\(n\)番目の文字に割り振られた数が \(m\) だったら、\(n\)番目の素数 \(p\) に対して \(p^m\) を作り、それらを全部掛け合わせるのである。そうするとゲーデル番号が与えられたら、素因数分解をすれば何番目の文字の番号が何か、計算できることになるのである。
これを \(\forall A \exists B\, \forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) という論理式の文字列で、実際にやってみよう。ちなみに、これは「すべての \(A\) に対して \(B\) が存在して、すべての \(X\) に対し、\(X=A\) と \(X\in B\) が同値となる」ということを意味していて、「どんな \(A\) に対しても、それ一つからできる集合 \(\{A\}\) が存在する」を意味している。
まず、理論で使用する文字のすべてに番号(コード)が振られているとする。ただし「番号」とは1以上の自然数のことである。解りやすさを優先すればアルファベットの文字 \(A, B\) の番号は並んでいたりすることが望まれるが、そういう便利さを無視して数学的に言えば番号の振り方は、(1) 違う文字には違う番号が振られている、(2) 振り方を文字列ごとに決めるのではなくて予め一通り決めておく、という二つの条件さえ満たしてさえいればよい。ここでは理論で使うすべての文字がどれだけあるか決めてないので \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) に現れる10個の文字に、たまたま次の表のように番号が振られているとしよう。
| 文字 | 振られた番号 |
|---|---|
| \(\forall\) | \(9\) |
| \(A\) | \(6\) |
| \(\exists\) | \(22\) |
| \(B\) | \(7\) |
| \(X\) | \(5\) |
| \((\) | \(4\) |
| \(=\) | \(2\) |
| \(\Leftrightarrow\) | \(13\) |
| \(\in\) | \(3\) |
| \()\) | \(1\) |
この表に従い次の様に文字列 \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) のすべての文字を振られた番号で置き換える。
| \(\forall\) | \(A\) | \(\exists\) | \(B\) | \(\forall\) | \(X\) | \((\) | \(X\) | \(=\) | \(A\) | \(\Leftrightarrow\) | \(X\) | \(\in\) | \(B\) | \()\) |
| \(9\) | \(6\) | \(22\) | \(7\) | \(9\) | \(5\) | \(4\) | \(5\) | \(2\) | \(6\) | \(13\) | \(5\) | \(3\) | \(7\) | \(1\) |
置き換えの結果、結局、 \[9\quad 6\quad 22\quad 7\quad 9\quad 5\quad 4\quad 5\quad 2\quad 6\quad 13\quad 5\quad 3\quad 7\quad 1 \] と言う数列ができた。
また、文字列 \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) の文字数は15なので、最初の素数 \(2\) から15番目の素数 \(47\) までの、15個の素数 \(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\) を用意する。そして、1番目の素数 \(2\) は1番目の文字 \(\forall\) の番号 \(9\) で、2番目の素数 \(3\) は2番目の文字 \(A\) の番号 \(6\) でという風に次の様にべき乗する。 \[2^9 3^6 5^{22} 7^7 11^9 13^5 17^4 19^5 23^2 29^6 31^{13} 37^5 41^3 43^7 47^1 \] そして、これらを掛け合わせるのである。 \[2^9\cdot 3^6\cdot 5^{22}\cdot 7^7\cdot 11^9\cdot 13^5\cdot 17^4\cdot 19^5\cdot 23^2\cdot 29^6\cdot 31^{13}\cdot 37^5\cdot 41^3\cdot 43^7\cdot 47^1 \]
その値は次の様な巨大な数になる。
これが文字列 \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) のゲーデル数である。そして、この数を因数分解すれば、逆に上の \(2^9 ・3^6 ・5^{22} ・7^7 ・11^9 ・13^5 ・17^4 ・19^5 ・23^2 ・29^6 ・31^{13} ・37^5 ・41^3 ・43^7 ・47^1\) が得られるから、これから数列 \(9{\quad}6{\quad}22{\quad}7{\quad}9{\quad}5{\quad}4{\quad}5{\quad}2{\quad}6{\quad}13{\quad}5{\quad}3{\quad}7{\quad}1\) が得られ、それを文字で置き換えれば元の文字列が再現できる。要するにゲーデル数とは文字列を一つの数でコードする方法なのである。また、同様に数列も一つの数でコードできるので、文字列の列、また、その列なども一つの数でコードできる。 TG などでの証明は、文字列である論理式の列で表されるので、そういう物もゲーデル数でコード化できるのである。
ゲーデルは、このゲーデル数というコードを使い、理論についての命題が自然数論の命題に翻訳できることを示した。つまり、「 \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) は TG で証明できる」とか「TG は完全である」とかの命題が、自然数についての命題に翻訳できることを示した。「 \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) は TG で証明できる」の場合でいえば、上に示した \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) のゲーデル数 \(622474263\cdots 0000\) についての命題に翻訳したのである。
驚くべきことには、ゲーデルの示したその翻訳には、自然数の積と和、等号、自然数の変数と定数以外には、論理の言葉、つまり、\(\forall , \exists , \Rightarrow ,\ldots\) のような論理記号しか含まれていなかった。これはそういう翻訳には、自然数の積と和、等号、自然数の変数と定数を使って、後は、「すべての自然数 \(x\) に対して…が成り立つ」「ある自然数 \(x\) が存在して…が成り立つ」「…ならば…である」とかの、論理的な言葉だけしか使われてなかったということである。こういう形の命題(論理式)を専門用語では「算術的命題」という。算術は算数の古い名称だが、確かに、こういう形の命題ならば「算数の命題」と言ってもよいだろう。
ゲーデルは、さらに「\(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) は TG で証明できる」のような命題(論理式)\(P\) についての「\(P\) は「数学の万物の理論」Tで証明できる」という形の命題については、次の事実が成り立つことを証明した。
この補助定理の意味を説明しよう。そのために「\(P\) はTで証明できる」という命題を翻訳してできた算術的命題を【\(P\) は T で証明できる】と書くことにする。この記号を使うと反映性の補助定理は次の様になる。
「数学の万物の理論」というからには、当然、自然数とその演算が定義できて、それについての命題が証明できないといけない。つまり、「算数」ができないといけないであろう。当然、「\(P\) は T で証明できる」を翻訳した算術的命題【\(P\) は T で証明できる】は T の命題となる。また、「\(P\) は T で証明できる」が成り立つならば、それを同値に翻訳した【\(P\) は T で証明できる】も真である。そして、「数学の万物の理論」であるからには、この真な命題【\(P\) は T で証明できる】は T で証明できないといけないはずである。つまり、こういう形の命題が真であることを「数学の万物の理論」は反映できないといけないはずである。これは「数学の万物の理論」である以上、当然のことであろう。ただ、「できないといけないはずである」では数学にならないので、ゲーデルは、これを丁寧に証明してみせたのである。
では、次節で、このゲーデル数による「万物の理論の中の万物の理論のモデル」を使って不完全性定理を証明しよう。
8. 不完全性定理証明のカラクリ3:ゲーデル式と第一不完全性定理の証明
第一不完全性定理の証明のポイントはゲーデル数を使って作り出した「万物の理論の中の万物の理論のモデル」を利用してできる自己反映的なゲーデル式 \(G\)、つまり、
この様な \(G\) は対角線論法という技法を使って作るのだが、それは初級編では難しすぎるので中級編にゆずることにして、そういうものが出来ることを前提にして第一不完全性定理の本質部分を証明してみよう。つまり、1931年の論文でゲーデルが\(\,\omega\)-無矛盾性という前提条件を使わず、無矛盾性だけを前提条件にして証明した次の事実を証明する。
他の理論でも証明は全く同じなので、 TG の場合で証明しよう。\(G\) が TG のゲーデル式であるとする。つまり、
背理法を使うために、「\(G\) が TG で証明できる」と仮定しよう。この背理法の仮定「\(G\) が TG で証明できる」に、前節の「反映性の補助定理」を適用すると、命題【\(G\) は TG で証明できる】が TG で証明できることが判る。
上に書いた等式で説明した様に、この命題【\(G\) は TG では証明できない】は \(G\) のことだから、背理法の仮定「\(G\) が TG で証明できる」は、「命題【\(G\) は TG では証明できない】が TG で証明できる」ということを意味している。これで、命題【\(G\) は TG で証明できる】と、命題【\(G\) は TG では証明できない】の両方が TG で証明できることが判った。
ところが、ゲーデルの翻訳では、「○○でない」という命題の翻訳【○○でない】は【○○】の否定として定義されていた。つまり、命題【\(G\) は TG では証明できない】は、命題【\(G\) は TG で証明できる】の否定なのである。したがって、 TG で、命題【\(G\) は TG で証明できる】とその否定が同時に証明できたことになる。
しかし、 TG は無矛盾だとしたので、これはあり得ない。よって背理法により、「\(G\) が TG で証明できる」が否定された。つまり、\(G\) は TG では証明できない。
そして、この背理法の結論「\(G\) は TG では証明できない」の翻訳はゲーデル式 \(G\) そのものである。つまり、ゲーデル式 \(G\) は正しいことになる。\(G\) は正しいが TG では証明できない命題である。
以上が、第一不完全性定理の最も重要な部分、「数学の万物の理論が無矛盾ならばゲーデル式 \(G\) は正しいが、その万物の理論でゲーデル式 \(G\) を証明することはできない」という事実の証明のカラクリである。
ゲーデルは、これの他に「\(\omega\)-無矛盾ならばゲーデル式の否定 \(\lnot G\) も証明できない」を証明したわけだが、中級編で解説するように、その証明は、Tが \(\omega\)-無矛盾だと、前節の「反映性の補助定理(書き変え)」の逆である、
実は\(\,\omega\)-無矛盾という条件は、「反映性の補助定理の逆」と非常によく似た形をしていて、その一般化になっている。実際、\(\omega\)-無矛盾性という条件から「無矛盾かつ反映性の補助定理の逆が成り立つ」という条件を証明できる。そして、このより弱い条件でTが不完全であることを証明できるわけである。そのため、ゲーデルは「反映性の補助定理の逆」が証明できなかったために、その命題を簡単に証明できて、また、その命題より自然に見える\(\,\omega\)-無矛盾性を考え出して前提条件にしたのではないかと勘ぐりたくもなる。しかし、実際には、そうではないだろう。この \(\lnot G\) の証明不可能性を示すためだけに使うには不必要に強い条件である、\(\,\omega\)-無矛盾性という条件は、おそらく、ゲーデルが一階算術の無矛盾性を用いて二階算術の無矛盾性の証明を試みるなかで考え出されたもので、第一不完全性定理発見の経緯を我々に示してくれる痕跡なのであろう。これについては中級編で説明する。
9. 不完全性定理の歴史的背景:ヒルベルト計画
ゲーデルは、なぜ不完全性定理を証明したのだろうか。それには長い歴史的背景がある。少なくとも19世紀中ごろからの数学の歴史が、その背景にあり、少し大袈裟にいえば、そのルーツはデカルト、ライプニッツの時代に遡ると言ってもよい。
そして、不完全性定理は、数学者に「哲学的な問題は考えても無駄だ、それは無視してよい」というお墨付きを与えるもので、デカルトやライプニッツが象徴する数学と哲学の伝統的関係を考慮すれば、西洋数学の長い歴史における大きな転回点だったのである。本節から、それについて説明しよう。
ホーキングは「物理学の万物の理論」とは「有限個の法則で物理世界の現象のすべてを説明できる無矛盾で完全な理論」だと言っている。そして、ホーキングは物理学者は万物の理論を追い求めるとした。ただし、ホーキングが、最初、そういう理論の存在を期待しながら、ゲーデルの不完全性定理を引き合いに出して、あっさりと180度転回の宗旨替えをしてしまったように、完全と言っても物理学者が知りたいと思うことを説明できれば良いのであって、本当に何でもかでも解決できる理論が欲しいということではないだろう。
つまり、ビッグバン以前の量子力学的な「極小宇宙」から「現在の巨大な宇宙」までの歴史を理解できたりすれば良いのであり、「2050年5月8日0時0分の富士山頂の気温」は予想できなくてもホーキングは気にしなかったはずである。こういう「超長期の天気予報」は、予報に使う気候モデルは古典物理学に従う決定論的なものでありながら、非線形系のカオス現象という数学的現象のために、大きな精度で予測することは不可能だと言われている。映画「ジュラシックパーク」にもカオス理論が専門の数学者マルコムが登場するほど有名な話なので、ホーキングも当然それは知っていたはずだが「万物の理論」について語る時、そういうものを全く問題にしてないことからも、これはうかがえる。
また、無矛盾と言っても、それは現状の一般相対性理論と量子力学の矛盾的関係が解消されることであり、万物の理論が未来永劫絶対に矛盾しないということをたとえば数学を使って証明したいという話ではないだろう。物理学者が理解したいのは物理世界である。一方物理学の理論そのものは物理的な「もの」でさえない。そういう非物理的なものの性質を数学的に証明するという事は多くの物理学者の興味ではないに違いない。おそらく、そういうことをしようとする物理学者は変人扱いされるだろう。

ヒルベルトは物理学の研究にも取り組み、アインシュタインは一般相対性理論研究の時期、ヒルベルトをライバルとみなした。しかし、アインシュタインが一般相対性理論を完成させた後、ヒルベルトは物理学から去り、「ヒルベルト計画」というプロジェクトに専念した。ヒルベルトの23の数学の問題の第2問題は「算術の無矛盾性の証明」であるが、ヒルベルト計画はこの第2問題やそれに関連する問題を数学で解こうというプロジェクトであり、とくにそういう理論の無矛盾性と完全性の証明がその最重要課題だったのである。
第2問題の「算術」は古い言葉づかいであって、実数の理論のことである。実数の理論は「万物の理論」のさきがけ PM の部分理論である第二階算術というものと同じであることがわかり、ヒルベルトは、これの無矛盾性を示す計画をたてたが、まずは、さらにその部分理論である第一階算術というものの無矛盾性を証明する計画を立てた。この研究は前例のないもので最初使える方法論も無かったので、やりやすいケースから段々と方法論を開拓しつつ問題を解決しようとしたのだろう。

この様な経緯で、大数学者ヒルベルトにより自然数の理論である第一階算術が無矛盾で完全であることを示すプロジェクトが開始された。このプロジェクトは当時の若く優秀な数学者たちの関心を引き、たとえば、数学、量子論、コンピュータ開発、原爆開発、数理経済学など様々な分野で重要で膨大な仕事をしながら、懸命に努力している所が見られないため、夜悪魔が来てノイマンの代わりに論文を書いているとまで言われたというジョン・フォン・ノイマンもこの計画に参加していた。
この万能の天才ノイマンが数学者として最初に本格的に取り組んだ研究分野が集合論で、実はNBGのNはノイマンのNで、先に紹介した集合による自然数の定義も、すべての集合が空集合を出発して作られていることにしたのもノイマンである。ノイマンが、これらの仕事を成し遂げたのはまだ20代前半のころで、20代半ばにもなると、若き天才としてその名は広く知られるようになっていた。
ノイマンはヒルベルトの学生ではなかったが、ヒルベルトを深く尊敬し、たとえばヒルベルトが開拓したヒルベルト空間論を使っての量子力学の最初の数学的基礎付け(ディラック-ノイマン公理系)など、その仕事にはヒルベルトの影響が強くみられる。その様なノイマンは、当然ながらヒルベルト計画にも深く関与し、1928年に第一階算術のさらに部分となる理論の無矛盾性を証明する論文を出版している。
ただ、ノイマンは完全性については懐疑的だった。彼は1928年の論文で「第一階算術の様な理論が完全ならば数学の問題が計算問題に過ぎなくなってしまう」と、ホーキングの「物理学の終」のような懸念を書いている。数学がトリビアルになる、それはノイマンには信じがたいことだった。チェスや碁などをプレイするAIは基本的には可能な手をすべて網羅して虱潰しに調べているということを知っている人は多いと思う。実は、これと同じことが原理的には簡単に第一階算術、さらには、TG, ZFC 等の「数学の万物の理論」に対して行えるのである。
つまり、すべての証明を網羅的に作成して、それの結論が与えられた命題自身かその否定であるかを虱潰しに調べるアルゴリズムが簡単に書けてしまうのである。そのため、もしそれらの理論が完全ならば、その理論の言語で表現できる問題なら必ず有限時間内に、それ自身かそれの否定の証明が見つかって真か偽か分かってしまう。そんな馬鹿な、というのがノイマンの考えであったらしい。そして、三年後にゲーデルにより不完全性定理が発表されたのだから、ノイマンは正しかったのである。実は、第一不完全性定理について、最初にその詳細を知った数学者は、そのノイマンだった。
1930年9月、ヒルベルトの生地ケーニヒスベルクでドイツ科学界の大きな学会が開かれた。ヒルベルトも参加し「自然認識と論理」という講演を行い、それを「我々は知らねばならない。我々は知るであろう」と結んだ。これは彼の墓碑銘でもある有名な言葉だが、その意はヒルベルト計画の目標「数学者は数学の万物の理論に到達できる。そして、到達できたことを証明できる」ということだったであろう。
この同じ学会で数学の基礎付けについてのシンポジウムがあり、ノイマンがヒルベルトの代理の様な立場で講演を行った。そして第2部のパネル・ディスカッションの最中、ある若者が「正しいが数学の理論では証明できない命題が存在する」と発言した。これが弱冠24歳のゲーデルだったのである。彼はこの年ウィーン大学で現在「一階述語論理の完全性定理」と呼ばれている定理を証明する論文で学位を得て、その成果を発表するためにこの学会に来ていたのである。この定理もヒルベルト計画の一部とも言えるもので非常に重要な定理である。
そして、ゲーデルは、この頃、すでに第一不完全性定理の証明を発見しており、議論の内容にうながされて、その未発表の新発見を口にしたのである。ノイマンは自らの懸念がこの新人数学者によりすでに証明されていたことに驚き、シンポジウム後にゲーデルに根掘り葉掘り聞いたと言われている。
10. 第二不完全性定理
ノイマンはベルリンに帰った後もゲーデルの成果を反芻したようだ。この時、ノイマンがゲーデルから第一不完全性定理についての詳しい証明を書いたものを受け取っていたとは考えにくい。おそらく、この稀代の天才はケーニヒスベルクでゲーデルから口頭で聞いた話だけで、第一不完全性定理の詳細を自身で再構成してしまったのだろう。そして、その結果、ある別の結論を、それを使って証明することに成功した。第二不完全性定理である。
第一不完全性定理はヒルベルト計画の大きな目標であった完全性と無矛盾性の内、完全性が成り立たないということを示していた。そして、この第二不完全性定理は無矛盾性の方もヒルベルトが希望していた様な方法では証明することができないことを意味していた。
第一不完全性定理はヒルベルトの願に反して完全性が成り立たないことを示していた。一方、第二不完全性定理は無矛盾性が成り立たないとか、無矛盾性は証明できないという定理ではない。実際、たとえば ZFC の無矛盾性は、この当時、タルスキが開拓していたタルスキ意味論という理論を使うと、 TG で簡単に証明できてしまう。しかし、ZFC が無矛盾である限り、 TG では証明可能なそれをZFC 自身では証明できない、第二不完全性定理はそういう定理なのである。
この様に無矛盾性の証明というものは可能であり、現代の数学の立場からすればそれで十分である。しかし、ヒルベルトの意図していた無矛盾性証明には現代の数学では無視される哲学的側面があった。ヒルベルトの意図した無矛盾性証明では、単に無矛盾性を証明したというのでは不十分で、無矛盾性を哲学的に適切な方法で証明する必要があった。たとえば、ヒルベルトの意図からすると、ある理論の無矛盾性を、その理論自体でを証明しても意味が無い。その理由は、疑われているものが自分は潔白だと主張しても人は信じてくれないからである。
ある組織、例えば政府とか企業で書類の改竄が疑われたとしよう。改竄は組織のトップの指示かもしれないし、組織ぐるみかもしれない。だから、組織のトップが「社内で調査しましたが、改竄の事実はありませんでした」と発表したとことで疑惑は晴れない。もちろん、その組織やトップを信用している人には、これで十分なのだが、そうでない人に取っては、こういう発表は何らの意味も持たないことは我々が日々経験していることである。
そういう時に疑惑を晴らそうとしたら、世間も信用を置くような委員会を組織して、その委員会に調査検証してもらうしかない。そういう委員会は、組織の外部者から構成されるのが望ましいが、例えば、組織の中に世間の信頼を一手に引き受けている様な人物がたまたまいて、改竄の時期にはまだその組織に属して無かったなど、その人物の関与がないことが明瞭だったときには、その人物を中心として組織の内部に委員会を作っても多くの人は納得するに違いない。
数学の理論の場合も同じである。数学の理論Tの無矛盾性に疑問が生じたならば、無矛盾性を疑われていない理論Aを使って無矛盾だと証明すればよい。もちろん、Tの無矛盾性が疑われているのだから、TはAの役割はできない。しかし、Tの疑わしい部分を削って、信用がおける小さな部分だけを残し、それをAとして使うのならばよいだろう。
ゲーデルは、1938年に行ったある講演で、こういう方法で行う無矛盾性の証明を「還元」Reduktion と呼び、部分理論ではない他の信用ができる理論で行う無矛盾性の証明を「置換」Ersetzung、あるいは「シフト」Verschiebung、と呼んだ(ゲーデル全集第三巻112頁)。そして、どちらも数学的には大きな意味を持つが哲学的には(ゲーデルは「認識論的」と言っている)還元の方が望ましいと主張した。その理由をゲーデルは詳しくは説明していないが、置換・シフトでは主観の問題が入ると言っている。つまり、置換・シフトで別の理論に無矛盾性を転換するにしても、すべての人が納得するような転換先があるとは限らないのである。
還元も、見かけ上は部分理論であっても、その部分で全体を代替することができるという事は良くあることなので、還元で無矛盾性が証明できたとしても、それだけで良いのではない。しかし、還元ならば、少なくとも「AはTの部分である」という、主観に依存しない条件が追加されている。おそらくゲーデルは、それ故に還元の方が哲学的には望ましいと考えたのであろう。また、ゲーデルがその講演で引用している様にヒルベルトがその様な条件をみたす理論A(ヒルベルトは「有限の立場」と呼んだ)で無矛盾性証明を実行すると明言していたことも大きいだろう。
しかし、第二不完全性定理によれば、「数学の万物の理論」は無矛盾ならば、自分自身の無矛盾性を証明できないのである。つまり、「見かけ上の部分理論」でさえ無矛盾性証明をできないのだから、「真に小さく削減されて信用がおける部分理論」では当然無矛盾性証明はできない。つまり、第二不完全性定理はゲーデルの1938年の講演の意味での「哲学的に望ましい還元による無矛盾性証明は不可能だ」という定理なのである。
ノイマンは1930年11月20日にゲーデルに手紙を書き第二不完全性定理の発見を伝えた。ノイマンはその9日後に再びゲーデルに手紙を送り、ゲーデルからの手紙に感謝するとともに、ゲーデルが既に第二不完全性定理を証明していたからには、彼は自分の研究を発表することはないと書き送っている(残念ながら、このゲーデルからノイマンへの手紙は失われている様だ)。そして、ノイマンは、この手紙の末尾に、これでヒルベルトの無矛盾性証明というゴールの不可能性が示されたという意味のコメントを書いている。
この後、ゲーデルとノイマンの間で二つの不完全性定理についての手紙のやり取りが暫く続くことになり、1931年1月12日にはノイマンがゲーデルに論文のゲラ刷りを受け取ったことへの感謝を書いている。その論文が、第一不完全性定理の詳細な証明と第二不完全性定理の証明のスケッチが書かれた、ゲーデルの歴史的な論文「Principia Mathematica と関連する体系の形式的に決定不可能な命題について I」であった。
ゲーデルは、このノイマンとの書簡による議論では、「第二不完全性定理によりヒルベルトの無矛盾性証明の計画の望みはついえた」というノイマンの意見に強く反対している。彼の歴史的論文の末尾には、第二不完全性定理はヒルベルトの計画を否定するものではないと書かれていたのである。
しかし、その後、ゲーデルは意見を変えて、1933年12月のアメリカ数学会での講演では、ノイマンの意見に同調する様になる。とはいうものの、この講演の末尾では、まだ1938年の講演の意味での「置換」「シフト」による無矛盾性証明への大きな期待が語られている(ゲーデル全集第三巻53頁)。
ところが、1938年の講演では、その様な「置換」「シフト」による無矛盾性証明の数学的意味は非常に大きいとしながらも、哲学的意味は大きく減退してしまったと言うようになる。実は、1938年の講演のテーマは、後の1950年代になってようやく公表されることになる「汎関数解釈」というものを用いるゲーデル自身によるそういう数学的に重要な「置換」「シフト」による無矛盾性証明だったのである。
ノイマンの様な優秀な若者たちがヒルベルトの無矛盾性証明などの計画に引き付けられたと書いたが、実は、ゲーデルもその一人だった。ゲーデル自身が無矛盾性証明に挑戦していたのである。
当時、ヒルベルトは、彼の弟子により第一階算術の無矛盾性証明は実質的には達成されており、次は第二階算術の無矛盾性証明だと公言していた。もちろん、これは誤解なのだが、ゲーデルはヒルベルトの言う事を信じ、第二階算術に対する無矛盾性を、第一階算術の無矛盾性に還元することにより証明しようとしたらしい。しかし、その試みの中ではからずも第一不完全性定理を発見したらしいことがハオ・ワンがゲーデルから聞き取ったことを書き残したものからわかる。
ゲーデルはヒルベルトの無矛盾性証明の可能性とその哲学的意義に大きな期待を寄せていたのである。1938年に自身の第2不完全性定理で、無矛盾性証明の哲学的意味が減退したという議論をした時でさえ、望んでいたことが何かの理由で不可能となった場合の残念な気持ちを表すときなどに使われるドイツ語の非現実話法というものを使って、「もしヒルベルト計画が実行できていれば、それは疑いなく偉大な認識論的価値をもっていたのだが」と言っており、その無念さが伝わってくる。
ところが、驚くべきことに、1961年ごろに書かれたとされる哲学講演の原稿(ゲーデル全集第三巻374-387頁)では、ゲーデルは、そのヒルベルト計画を、本質的にイデア論的・形而上学的なものを、それと正反対の懐疑論的・ニヒリズム的立場で合理化しようとした「その奇妙な混合体」jenes merkwurdige Zwitterding と呼ぶ様になる。この時ゲーデルは、哲学的に考えればヒルベルト計画は必然的に失敗する運命にあった奇妙な計画であって、彼の不完全性定理は歴史的必然だったのだ、といわんばかりの主張をしているのである。
1930年代のゲーデルの無矛盾性証明に対する態度からするとただただ驚くしかない。このゲーデルの「奇妙な混合体」とは、正確には何の事だろうか。そういう見方は正しいのだろうか。また、ゲーデルの心境の変化は何故だろうか。これらを知りたくて行ったのが、本サイトで紹介しつつある私の研究であり、それを説明するのには時間がかかる。また、この講演原稿を現在和訳中で、既に訳した部分をこちらで公開している。ただし、全集にはドイツ語のオリジナルだけでなく英訳も掲載されているので、英語が十分に読める人は、そちらで読める。
ゲーデルもノイマンもヒルベルト計画は不可能だと結論するようになり、この二人の数学観は大きく変わったようだ。ゲーデルはいつ自分がなぜ考えを変えたかということを語っていないし、それを推測し解説することは、このサイトの重要な目的の一つである。一方のノイマンは「数学者」というエッセイで彼の数学における真理観が三度変わったと、その経緯も含めて説明している。そして、それの最後の変化が不完全性定理によるものだったのである。ノイマンの最後の数学的真理観、あるいは、数学存在論は「数学はエレガントで有用な結果を生み出している。その信頼性に絶対的に厳密な保証はないものの、その基礎は電子の存在と同じ位確かだ」という現実的なものだった。おそらく、現代の数学者の多くは彼の立場に共感を覚えるだろうし、元数学者の私もそうである。
しかし、若きノイマンやゲーデルを強く引き付けたヒルベルト計画、特に無矛盾性の証明とはなんだったのだろうか。数学的真理は、あらゆる学問的真理の内で、最も信頼できるものではないのだろうか。なぜ、わざわざ数学の理論が無矛盾だと証明したいと考えたのだろうか。
ゲーデルの「還元」を説明するために、組織の疑惑のたとえ話をしたが、実は堅固なはずの数学が疑惑に包まれた時代があったのである。無矛盾性証明の目的は、その疑惑を晴らすためだった。次に、これについて解説しよう。しかし、そのためにはちょっと準備が必要である。この解説をするには「数学の万物の理論のルーツ」についての知識が必要なのである。しかし、以前は欧米の大学では学問の基礎のひとつとして教えられ、また、日本の大学でも昭和の時代のころまでは、教養科目として広く教えられていたそのルーツが、大学教育の変化のために、特に日本では全くと言って良いほど教えられなくなり、その知識を持っている人が壊滅状態にある。そのため少し詳しい解説を次節で行うわけである。そして、その次節で解説する「数学の万物の理論のルーツ」とは古代以来の西洋の知識体系の基礎といえるアリストテレス論理学なのである。
11. アリストテレス論理学その1:名辞の学
ZFC, NBG, TG は二つの直接のルーツを共有している。集合論と記号論理学である。そして、さらに、この二つの直接のルーツの共通のルーツが古代ギリシャ以来連綿と受け継がれてきたアリストテレス論理学であった。つまり、「数学の万物の理論」の真のルーツは哲学の特殊な一分野であるアリストテレス論理学なのである。
アリストテレス論理学は、今日でもアメリカの大学ではリベラル・アーツ科目として教えられている事が多く(参考)、日本の大学でも1980年代に入るころまでは良く目にする科目だった。しかし、現在はほぼ絶滅状態である。そのためアリストテレス論理学を知る人は現在の日本ではほとんどいないので、この節と次節で、それの二つの側面を簡単に説明し、また、それぞれの側面が集合論と記号論理学を生んだ歴史の話をする(アリストテレス論理学のより詳しい解説は、本サイトの論理学の歴史:アリストテレス論理学入門を兼ねてを参照。)。
アリストテレス論理学は伝統論理学、項論理学 Term Logic などとも呼ばれる。アリストテレスという名前はついているが、ルーツがアリストテレスだというだけで、現在目にすることが出来る様な体系にまとまったのは1662年に出版された教科書「論理学、あるいは思考の技法」でのことである。この教科書はポール・ロワイヤル論理学と呼ばれることが多い。著者の一人のアルノーは哲学者としても知られており、近代哲学の影響もみられ、19-21世紀の大学科目としての論理学と異なり形而上学、存在論の要素が強い。
アリストレス論理学では命題の基本形は \(S\) be \(P\) という二つの名詞を be 動詞で結んだ様なものだと考え、他の動詞や形容詞を使う命題も、この形に変形して考える。たとえば、「人は死ぬ」は、「人 be 死ぬもの」と考える。\(S\) と \(P\) を名詞と呼んだが、正確にはこれらは名辞 term と呼ばれ、名詞という言葉とは区別され、概念の様なものだとされる。そして名辞には、内包と外延という二つの側面があり、内包はそれをそれ以外から分かつ条件、たとえば人ならば「道具や言語を使う二足歩行の動物」であり、外延は、その条件を満たすものすべてを集めたものとされる。
名辞は哲学の概念だから、それについての不明瞭な議論が多く相反するような説明がされていることも多い。しかし、それらを無視して、数学の集合の記法を使って説明すれば、10以下の偶数の集合は、\(\{n|\, n\) は \(2\) の倍数で \(n\leq 10\}\) という内包的定義と呼ばれる方法と、\(\{2, 4, 6, 8, 10\}\) という外延的定義と呼ばれる方法の二通りの方法で定義できることは高校数学でも学習することである。哲学的には内包的定義の内包の方が外延的定義の外延より本質的とされたが、数学の集合の概念を知っている現代の私たちにとっては要するには現代的な集合そのもの、つまり、物の集まりである外延の方がわかりやすいし、「数学の万物の理論」の成立に大きな影響を持ったのも外延なので、名辞とは内包的な定義を伴うこともある外延、つまり「モノの集まり」である集合のことだと思うことにしよう。
そうすると、\(S\) be \(P\) は部分集合の関係 \(S\subseteq P\) になる。つまり、「人は死ぬものである」あるいは、「人 be 死ぬもの」とは、\(H\) が人(humans)の集合で、\(M\) が死ぬもの(mortal beings)の集合であるとき、\(H\subseteq M\) のことなのである。
命題には主語が上の例の「人」の様な一般名詞でなく「ソクラテスは人である」の様に固有名詞のものがあるが、その場合「ソクラテス」が表す内包は、古代ギリシャの一人の哲学者のことなので、その外延は、その哲学者を記号 \(s\) で表せば、\(s\) だけを要素としてもつ集合 \(\{s\}\) となる。その結果、「ソクラテスは人である」も部分集合の関係 \(\{s\}\subseteq H\) となる。
現代ならば \(s\in H\) という式で表す、命題「ソクラテスは人である」の \(\{s\}\subseteq H\) という表現は、この命題を「すべてのソクラテスは人である」という意味だと考える不思議なものである。そのため、アリストテレス論理学の教科書でも「変だ」「気持ちが悪い」と書いてあることさえある。しかし、伝統的にこの様に考えるのである。ちなみに、この様に表現したものをアリストテレス論理学の用語で全称肯定という。これを「あるソクラテスが存在して人である」とする解釈する特称肯定というものもあるが(次節で解説する)、こちらも気持ち悪い。
以上を使って、これが集合論につながった歴史を解説しよう。このテキストの最初の方で20世紀には集合を用いる抽象数学の登場により数学の形が大きく変わったと書いたが、そのルーツは19世紀中ごろにあり、他にも様々なルーツがあるものの最も重要なものは、ドイツ・ゲッチンゲン大学にいた二人の親友ベルンハルト・リーマン Bernhard Riemann とリヒャールト・デーデキント Richard Dedekind による数学の新スタイルだった。
デーデキントはリーマンより5歳若く、リーマンの天才を尊敬し、瞑想的ともいえるほどの性格だったリーマンの実生活を支え、リーマン没後は未発表だったリーマンの業績を出版した。また、デーデキントは、リーマンがその天才的直観で数学的基礎なしに自由に使って済ませていた集合の理論を、数学者 G.カントルとともに数学的に整備し、また、集合論とそれを用いる抽象数学を誰もが使える様にした。その意味で、集合論における後世への実際的影響は、リーマンよりデーデキントの方が大きいといえる。
しかし、そのデーデキントの数学の源泉は、盛んに数学や哲学について議論したとデーデキントが書き残しているリーマンに求めるべきだと考えられているし、デーデキント自身がそう考えていた。この様なことから、現在の数学史ではリーマンを集合論とそれを用いる現代数学の祖とする説が有力なのである。
そのリーマンの「集合」は幾何学的な存在で、リーマン没後にデーデキントが出版することになった1854年の「幾何学の基礎をなす仮説について」と言う歴史的な講演で登場した「連続多様体」である。今日の数学には、リーマン多様体、アーベル多様体、複素多様体、微分多様体など様々な「多様体」があるが、そのすべての出発点であり、この概念が後の数学に与えた影響は計り知れず、もしリーマンの多様体を用いる数学にルーツをもつ理論を全部消し去ったら、 TG の G のグロタンディエクの代数幾何学をも含む、現代数学の重要部分の多くが消えてしまう。それほどの影響力を持つものだった。
しかし、この時、リーマンは「連続多様体」以外に「離散多様体」に言及し二つを合わせて「多様体」だとしたのである。彼は連続多様体に属するものを「点」、離散多様体に属するものを「要素」と呼ぶとして、多様体は Begriff の一種だとした。このドイツ語の Begriff は概念と和訳されることが多いが、様々な訳語をもち、実は、その一つが名辞なのである。ドイツ語ではアリストテレス論理学を Begriff の論理 Begriffslogik とか Termlogik と呼ぶのである。つまり、「リーマンの集合」はアリストテレス論理学の名辞だったのである。
現代の数学では、位相空間論というものを使って、離散的と考えられる現代的な集合の上に、やはり離散的な集合を使って「位相構造」と呼ばれる「連続性」を導入する。そして、それをベースとして、その上に様々な構造を導入して多様体を定義する。しかし、位相空間論が登場したのは20世紀なので、それを使うことができなかったリーマンは、連続性をその多様体が持つ固有の性質の様にとらえて「連続多様体」と呼んだのである。
つまり、そういう位相構造がない「離散多様体」の方が現代の集合に近いものだったと考えられる。後に、デーデキントは、集合をどういう専門語で呼ぶかに迷っていたカントルに、リーマン由来の用語として「多様体」を使ってはどうかとすすめていることからも、リーマンとデーデキントは、「多様体」を一般的には現代の集合の様なものとして理解していたことが推測できる。
その後、リーマンは「連続多様体」を使い多くの偉業を成し遂げるが「離散多様体」を使うことはなかった。それを行ったのは、彼の親友デーデキントである。1872年まで出版されることはなかったが、デーデキントは、リーマンの講演から4年後には教育目的で、集合を使って実数を定義する方法であるデーデキント切断を考案している。ただし、一般にも知られるこの有名な切断の概念であるが、その出版の前年に公表された彼のイデアル理論に比較すれば、後世に対する影響力ははるかに小さい。言い換えれば、イデアルという概念の後世への影響力は極めて大きいのである。
イデアルの概念は整数論への応用のために考えられたもので、ある種の拡張された数にあたるものを既存の数の集合として定義する方法であった。それは例えば整数の集合として定義され、イデアルの二つの要素の和が再び、そのイデアルの要素となる、イデアルの要素の倍数は再び要素となるという、簡単な二つの条件を使って定義される。
しかし、この単純なアイデアの技術的影響力はすさまじく、現在は整数論を超えて多くの分野で使用されているため、リーマンの多様体の思想に影響を受けたものを禁じれば現代数学の精華の多くが消えてしまう様に、このイデアルというテクニックを禁じれば同じく現代数学の多くが消えてなくなるのである。
先にイデアルを集合と呼んだが、デーデキント自身は「システム」 System (ドイツ語の発音は「ジステーム」に近い)という言葉を使った(デーデキントのイデアルの定義は、これの180頁にある)。デーデキントへのリーマンからの影響を考えれば、デーデキントのシステムもアリストテレス論理学の名辞であったことは明らかだろうが、それには直接的証拠もある。
1888年、デーデキントは「数とは何か、何であるべきか」Was sind und was sollen Zahlen?(この岩波文庫の第2篇)という小冊子を出版してシステムを使って自然数の理論を基礎づけた。その序文でデーデキントは実数などが自然数を使って基礎づけられたが、自然数より簡単な数学の概念がない以上、自然数は論理学 Logik を使って基礎づけるしかないと書いたのである。
現代から見れば、この Logik を数学への応用を意識した記号論理学と解釈したいところだが、この書の最初のバージョンが書かれた1872-8年には、そういうものはまだ存在しておらず、後で説明するブールなどによるアリストテレス論理学への数学からの応用、つまり哲学への数学の応用しかなかった。また、デーデキントは、この書でシステムを多様体とも呼んでいる。そして何より、この書で集合間の関係として \(\subseteq\) にあたるもののみを基本記号として使い、伝統的な論理学の考え方に従い、\(s\) が集合 \(S\) の要素であるとき \(s\subseteq S\) が成り立つとしたのである。
この書には、「私の思惟の世界」を使う無限集合の存在証明など、彼の Logik が哲学の一部であるアリストテレス論理学であったことの証拠が他にもあるが、それらは???で論じることにして、ここではこれで「19世紀ドイツの高等教育を受けた者ならば常識として知っていたアリストテレス論理学を利用して、集合を使う数学の系譜がリーマンとデーデキントにより開始された」という歴史の話を終わる。
ちなみに「集合論の祖」としては、デーデキントと交流があった彼より14歳若いドイツの数学者ゲオルク・カントル Georg Cantor の名前があがることが多いが、これは純粋に集合を研究する「純粋集合論」というものについては正しいが、ここで問題にしている「集合を多用する数学」である抽象数学の基礎としての集合論という点では正しくない。
リーマンとデーデキントの「集合論」を禁止するという思考実験をすれば現代数学の多くが消えてなくなるのだが、同様の思考実験をカントルの集合論のコアである超限順序数・超限基数の理論で行ってみると、ほとんどの現代数学の理論が生き残る。代数、幾何、解析などとの接点が少ないカントルの超限順序数・基数の理論は、それを避けて数学を行える方法が発明されているために、それを禁じられても現代の数学の主要部分はほとんど無傷で残るのである。
そのためもあるのだろうが、現代の数学者には、カントルの集合論の数学への貢献を低く見積もろうとする人が少なくない。カントル集合論に特に色濃く漂っている「哲学由来」故の雰囲気を感じ取り、それに違和感を覚えるという理由もあるのかもしれない。しかし、19世紀以来の実際の歴史を検討すれば、カントルの集合論、特に超限順序数・基数の理論が、ZFC, NBGの成立に繋がったことは明らかである。そして、 ZFC やNBGの存在のお陰で数学者が数学の基礎について思い煩う必要がなくなったという現実の歴史を見れば、カントル集合論の歴史的意義の大きさは明らかである。その意味で、カントル集合論の意義を無視するのは間違いである。
しかしながら、本節の目的は、集合論というものが哲学の特殊な一分野であったアリストテレス論理学から生まれたということを解説することなので、カントルが本格的に登場するのは次節のラッセル・パラドックスの話でのこととなる。
さて、ここで話を転じて次節で「推論の分類学」としてのアリストテレス論理学のもう一つの側面と、それから記号論理学が生まれたという話をしよう。
12. アリストテレス論理学その2:推論の学
初期の抽象数学で、アリストテレス論理学の名辞(概念)が集合の役割を果たしたことを前節で解説したが、アリストテレス論理学の一番の本体は、主語 Subject S と述語 Predicate P という二つの名辞から構成される命題を使う推論の学であるシロギズムである。シロギズムは日本語では三段論法と呼ばれ、たとえば、A be B, B be C と言う二つの命題を前提として、それから A be C を結論することが論理的に正しい推論であるかどうかを検討する学である。有名な「ソクラテス は 人間、人間 は 死ぬもの、よって、ソクラテス は 死ぬもの」という先ほど部分集合関係の推移律として説明した推論は、こういう三段論法の推論の一例である。ただ、これは実は「the 三段論法」ではないのである。
デーデキントの「論理学」 Logik では、主語と述語にあたる集合の関係は、\(A\subseteq B\) を基本としていたので、部分集合の関係 \(\subseteq\) の推移律にあたる「ソクラテス は 人間、人間 は 死ぬもの、よって、ソクラテス は 死ぬもの」しか考えられない。デーデキントの数学のためにはこれで十分だったが、フランス語、ドイツ語、英語のような自然言語で書かれた文章における推論の学であったアリストレス論理学では、たとえば「数学者でない哲学者が存在する」というような文も表現できないといけない。
実はアリストレス論理学では、二つの名辞 \(S, P\) から作られる基本命題を範疇命題 categorical proposition と呼び、それには4つのモードがあって、そのモードが一つ指定されて、初めてその命題の意味が確定すると考える。つまり、デーデキントが使った命題の解釈がすべてではないのである。この4種類のモードは英語の様な言語の構造を色濃く反映していて、日本語を例にして説明すると不自然なものになるので英語の文を例に使って説明しよう。
アリストテレス論理学では二つの名辞 \(S, P\) を考えて、\(S\) be \(P\) のような命題を作るが、その命題には、量 quantityと質 quality というモードがあると考える。量は全称 universal か、特称 particular のどちからで、質は肯定 affirmative か、否定 negative のどちらかである。その結果、モードは、2×2種類、つまり、4種類あることになり、それらを全称肯定 universal affirmative, 特称否定 particular negative などと呼ぶ。
そして、\(S\) be \(P\) という範疇命題のモードとして特称否定を指定するときには、\(S\) に some を、\(P\) には、not を、それぞれつけて、some \(P\), not \(P\) として、これを be 動詞で結んで、some \(S\) be not \(P\) という意味だとするのである。例えば、S が数学者 mathematicians, P が哲学者 philosophers ならば、「Some mathematicians are not philosophers」となって、デーデキントが使った形の「命題」では表せなかった文になる。全称肯定の場合は、\(S\) には all をつけて、\(P\) はそのままにする。つまり、「All mathematicans are philosophers」となって、デーデキントが使った形になる。ここまで説明すれば残りの全称否定、特称肯定の意味も明らかだろう。
そして、シロギズムの理論とは、\(A\) be \(B\), \(B\) be \(C\), \(A\) be \(C\) という三つの命題のモードを指定したとき、\(A\) be \(B\), \(B\) be \(C\) が正しいとして、\(A\) be \(C\) を推論することが正しいかどうかを決定する学なのである。例えば、\(A\), \(B\), \(C\) のモードが三つとも全称肯定ならば、すでにデーデキントの論理学の所で説明したように、それは正しい推論である。しかし、\(A\) を特称肯定、他の二つを全称肯定にすると、some \(A\) are \(B\), all \(B\) are \(C\) → all\(A\) are \(C\) となって正しい推論とはならない。\(B\) がすべて \(C\) でも、\(B\) でない \(A\) がありえるので、それが \(C\) でないかもしれないからである。
推論のパターンは4×4×4の64通りで、アリストテレス論理学を学ぶということは、その64通りの内、どれが正しいかを記憶することであり、たとえば四つのモードにAEIOという符丁をつけて、母音のアルファベットだけとりだすとAEIOの長さ3の組みわせとなる単語に当てて記憶するというようなことが行われた。ちなみに、全称肯定の符丁はAなので、全て全称肯定の場合を表す単語はBARBARAであった。
もちろん、そんなものが面白いわけはなく、これを統一的に理解できる数学的方法が19世紀に発明された。その一つが高校でも学習する集合のベン図である。実は、イギリス・ケンブリッジ大学のジョン・ベンが、1880年の「命題と推論の図的機械的表現について」で、ベン図の体系的な使い方を提唱したとき、それは集合論のためではなくアリストテレス論理学の学習をする際の道具としてだったのである。それがアリストテレス論理学が忘れ去られて、すっかり集合論の道具になっている。これも集合論とアリストテレス論理学の深い関係を示唆するエピソードだろう。
そして、もう一つがこれもイギリスの数学者ジョージ・ブールが1847年に出版した「論理学の数学的分析」の理論だった。その題名が表すように、ブールの理論は数学を使って論理を理解・運用するためのものだった。
ブールの理論では、代数式を使って範疇命題を表すことにより、正しい推論を代数計算で導出できた。たとえば、\(X, Y\) が名辞であるとき、ブールは、それを表す代数の変数 \(x, y\) を導入し、名辞を集合と考えたときに共通部分にあたる名辞を \(xy\) と書き、全称肯定モードの範疇命題を \(xy=x\) と表した。こう表せるのは、\(x\) が \(y\) の部分集合ならば、共通部分 \(xy\) は \(x\) であるし、そうなるのは \(x\) が \(y\) の部分集合のときだけだからである。そして、BARBARAは、\(xy=x, yz=y\) と仮定して、\(xy=x\) から \(xz\) の \(x\) に \(xy\) を代入して、\(xz=xyz=x(yz)=xy=x\) よって、\(xz=x\) と代数計算で求められる。
ブールの理論の特称の扱いは失敗しており、また名辞の割り算があるなど、色々と問題があったが、アメリカのパースや、自然数のペアノの公理のペアノなどの手を経て改良され、これが現代の記号論理学につながった。そして、その記号論理学の最初の完成形というべきものが次節で解説するラッセルの理論だった。そして、それは歴史上最初の「数学の万物の理論」でもあったのである。
デーデキントは1888年の著書で自然数の集合を作り出す際に無限集合の存在を証明することになり、そのために数学の範囲を超える、あるいは、当時の標準的な論理学の範囲さえ越えていたとも言って良い「私の思惟の世界」という集合を使った。しかし、ラッセルの理論は論理学の枠にとどまったままで自然数を作り出せるほど強力だったのである。ただし、それは強力すぎた。矛盾まで生み出してしまったのである。そして、それがヒルベルトの無矛盾性証明の計画を生んだのである。次節で、この話をしよう。
現在のブール代数の説明では、上のxy=xのxやyは命題を表すと説明されることがある。しかし、ブールのオリジナルでは、それは名辞だったのである。実は現代の抽象代数学にブール代数(ブール束)という抽象代数系があり、ある集合の部分集合全体が、その例となり、それがブールのオリジナルの代数のアイデアと一致する。しかし、この現代代数学のブール代数の別の例として、命題の真偽の値(真理値)を表す1と0の代数があり、それが情報工学への応用で有名になって、今では「ブール代数=1と0の代数」と思っている人の方が多数派の様だ。集合と考えられる名辞を表す記号が命題の変数に置き換わってしまったのは、おそらく、この1と0の代数としての「ブール代数」が数学を超えて有名になったためだろう。また、ブールは新しい代数を生み出そうとしてブール代数を考えたと言われることがあるが、ブールのオリジナルを読むと、ベン図の目的と同様に、伝統的な論理学を数学的手法、特に機械的代数計算で基礎付け改良・拡張することが彼の目的だったように見える。
13. ラッセルの論理学とパラドックス
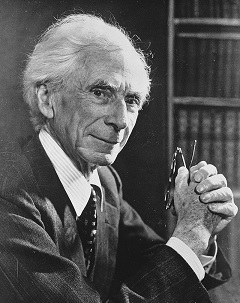
なぜヒルベルトが数学の理論の無矛盾性の証明をしようとしたか。それを説明するために前二節にわたりアリストテレス論理学と最初期の集合論と記号論理学の話をした。19世紀にアリストテレス論理学が数学の世界に入って行ったとき、最初、それは二つに枝分かれしたのである。そのひとつが第11節の名辞の理論を継承するリーマン、デーデキントの集合論、もうひとつが第12節のブールによるシロギズムの理論の数学化であった。
この二つは、前者が哲学の一分野とも言えた論理学の数学への応用、後者が逆に論理学の数学化であり、方向性がちょうど180度逆である。現代では記号論理学というと、その最大の応用先は数学そのものなのだが、最初の記号論理学であるブールの論理学は数学における推論をターゲットにして作られたものではなく伝統的論理学を数学の見地から理解するためのものだったのである。
しかし、この状況はブールの後に大きく二つの点で変わった。ひとつにはブールの論理学が伝統的論理学の枠を超えて、独自に進化を始めた。ブールの論理学では全称の「すべての…に対して」、特称「ある…が存在して」の理解は伝統的論理学の枠にとどまり、特に特称の扱いは成功していたとは言えないものだった。しかし、ブールが「かつ」を積で、「または」を和で表したことからのアナロジーで、全称が総積と特称が総和と対応することが認識され、全称、特称が肯定、否定から切り離されて独立して、第7節でゲーデル数の作り方の例に使った \(\forall A\exists B\,\forall X(X=A\Leftrightarrow X\in B)\) という論理式の全称量化子 \(\forall\) や特称量化子 \(\exists\) が生まれた。
そして、もう一つの変化として、この様な新しい仕組の論理学である記号論理学を数学に応用しようという気運が生まれた。ひとつにはペアノによる記号論理学での数学の証明の記述で、もうひとつがドイツの数学者で哲学者の G.フレーゲとイギリスの哲学者で数学者のバートランド・ラッセル B. Russell による論理だけで数学存在を作り出す試みであった。この内、これからの話に関係するのはラッセルの研究である。
先に PM という理論が最初の「数学の万物の理論」だったと書いたが、これはラッセルが、A.N. ホワイトヘッド A.N.Whitehead と共に表し1910-13に出版した三巻の著「数学原理」の理論のことであり、ゲーデルの歴史的論文の題名にある Principia Mathematica とは、これのことなのである。その Pricipia Mathematica より遡ること7年、ラッセルはThe Principles of Mathematicsという著書を出版している。題名は英語だが意味はラテン語の Principia Mathematica と同じ意味である。こちらは PoM と書くことにする。実は PM は最初、1903年の PoM の続篇として計画されたが、ある事情により全く新しい書物として出版された。その事情が数学の危機を決定的なものにした「ラッセル・パラドックス」の発見だった。
PoM は直接的にはペアノの論理学をベースにしておりシロギズムの正しい推論法則を少数の論理法則から導出することができた。そして、それはさらに19世紀に分かれたもう一つの枝を包含するものだった。ペアノは彼の論理学で、自身の微分方程式についての定理の証明などを記述したために、数学の概念を記述することができた。その際、彼は名辞、つまり、集合にあたるものと、その要素の関係を伝統的な論理学の \(\{a\}\subseteq A\) でなくて、\(a\in A\) と書くことを始めた。
ラッセルもこれを継承したが、それだけでなく \(a\in A\) の \(A\)、つまり、伝統的論理学では述語の名辞、つまりは、リーマン、デーデキントの集合についての理論を一挙に拡張整備した。その当時に、数学ではすでに集合の使用がかなり広がっていて、集合は様々な名前で呼ばれていたが、ラッセルは、それらとは異なるこれも伝統的な論理学で使われるクラスという言葉で「彼の集合」をよび、多くの哲学的議論をして、それを伝統的論理学の名辞や数学の集合と関連付けて説明した。
しかし、PoM の最大の特徴は、こういう論理学だけで数学的存在を定義できたことであった。すでに書いたようにデーデキントは1888年の著書で数学書に相応しくない哲学的議論をして、それを利用して自然数を定義した。彼にとっては、その書は「論理学の数学への応用」であったろうから哲学的議論が入っていても自然だったのかもしれない。
ところがラッセルは哲学を全く使わずに自然数とその集合を作ってみせた。ラッセルは、PoM で彼の論理学の基本概念や基本法則について哲学的議論を盛んにしている。しかし、命題を作り定義をし推論を行う、という PoM の論理学の実際的運用は全く数学化されていて、哲学的議論は全くなしに形式的規則だけで運用できたのである。そして、そういうもので彼は自然数を作った。
ラッセルは、例えば数2を「要素が丁度2個だけある集合の集合」で定義した。彼の用語に従えば、「要素が丁度2個だけあるクラスのクラス」だが、ここでは割り切って集合と書く。この集合の定義には「2個」という言葉が使ってあるので、2を定義するのに2を使っているから定義になっていないが、ラッセルは、「集合 \(A\) は要素を丁度2個だけもつ」という条件を「集合 \(A\) は \(x ,y\) という要素を持ち、\(x=y\) ではなく、また、\(A\) の要素は \(x, y\) だけである」と言い換えた。特称量化子などを使って論理式として書くと \(\exists x\exists y(x\in A\land y\in A\land \lnot x=y\land \forall z(z\in A\Rightarrow (z=x\lor z=y)))\) である。これにはどこにも数が使われていない。ちなみに、\(\in\) や \(=\) は当然ながらラッセルの論理学の一部であった。
同様なテクニックを使うと、「集合 \(A\) は集合 \(B\) に入っていない要素を一つ添加したものだ」ということを論理だけで書ける。それを使うと2より一つ大きい数というのを「一つ」を使わずに定義できる。そして、こういうテクニックを使うと自然数の集合までもが定義できて、それに対してペアノの公理を証明できるのである。(その詳細は??で解説する予定)
そして、ラッセルは、自然数から有理数、実数などを作り、解析学なども展開できることを示し、空間も定義した。ラッセルはすべての数学の理論を再構築して見せたわけではないが、ラッセルが実際に行った再構築の方法を見れば、その方法で既存の数学がすべて再構築できることは明白だった。そして、彼はさらには物理学の理論についての章まで書いた。もちろん、それは物理法則を表現できるだけで物理法則を論理的に導出できたわけではないが、ラッセルのすべてを飲み込もうとする意思を感じさせる章であった。
古代以来、ヨーロッパではそれについての様々な哲学的議論があった数学の基礎が、論理学という哲学の一分野を数学的に改良したものの上に堅固に建設されたのである。そして、その論理学は18-19世紀の哲学者カントが「アリストレス以来何らの進歩もない」と語った学問、つまり、完成され切ったはずの学問だったのである。この世でもっとも堅固な合理性といえる論理学のみで数学を基礎づけることができる。ラッセルが達成したはずだったこの数学の基礎付けの方法を、数学の基礎付けにおける論理主義という。
ヒューマニズムと自由主義についての著作でノーベル文学賞も受賞したラッセルは20世紀を代表する哲学者の一人で、政治活動でも有名で97歳で亡くなる直前までベトナム反戦運動を行っている。ラッセルはその波乱に満ちた生涯を大部の自伝に綴ったが、その中で、PoM の執筆期間を知的陶酔の時と呼んでいる。この世で何より信頼されている論理学のみを使って、古来より多くの数学者や哲学者の論争の的になっていた数学の基礎の問題を一挙に解決してしまったのだから当然である。しかし、彼は、その時期のすぐ後に人生で最悪の期間が訪れ、一度は自殺も考えたと正直に語っている。それが「ラッセル・パラドックス」の発見と、それによる PM の成立の期間であった。
PoMには「矛盾」The Contradiction という題名の奇妙な章、第10章がある。この第10章で、ラッセルはPoMの論理学に矛盾があることを示した。つまり自身の理論が破綻していると表明したのである。そうであれば幾ら古来以来の問題を解決しても仕方がないはずなのだが、ラッセルはこの問題は何かの勘違いのようなもので、まだ見つかっていないものの容易な解決法があると信じていたらしい。それで、その矛盾「ラッセル・パラドックス」とともに、PoMの論理学と数学の基礎付けを発表したのである。
先ほど、PoM は当時の伝統的な数学をすべて飲み込んだと書いたが、それは伝統的数学だけではなく、当時の新興数学だったカントルの集合論の超限基数・順序数の理論まで飲み込んでいた。カントルの集合論とラッセルの記号論理学はアリストテレス論理学から生まれて生き別れた兄弟の様なものだから、これは当たり前のことである。
そのカントルの集合論にはある問題が起きていた。カントルの超限基数論というのは、ラッセルが2を定義したのと同じような考え方で無限集合の「要素の数」(基数)を考える理論だった。カントルは無限集合には異なる基数があり、たとえば自然数の集合の基数は実数の集合の基数より小さいことを示し、また、どの様な集合に対しても、その基数より大きな基数を持つ集合が存在することを、対角線論法というものを使って証明した。ゲーデルがゲーデル式を作るために使った対角線論法である。(対角線論法とこのカントルの定理については中級編で解説する予定である。)
ところが、この対角線論法が困ったものを生み出した。現在、カントルのパラドックスと呼ばれているものである。カントルやラッセルの理論では、すべての集合の集合が認められていた。「集合」という語は名辞と考えられるから、これは伝統的な論理学の考え方からは自然であったろう。この「集合の集合」の基数は最大の基数だと簡単に証明できた。ところが、対角線論法を使えば、それより大きな基数を持つ集合があるはずなのである。つまり集合の理論が矛盾するのである。
ラッセルは、このカントルのパラドックスをカントルが従来の自然言語に頼る数学の証明や定義を使っていたことで起きた、ちょっとした勘違いの類だとおもったらしい。自分の精緻な論理学を使って分析すれば、間違いは直ぐに見つかるだろう。その様に思って分析を始めたラッセルが見つけたものは、パラドックスの解消法ではなく、煎じ詰められた「パラドックスのエッセンス」だった。つまり、カントルの超限基数の理論のような複雑なものを一切排除した彼の論理学の最も簡単な運用だけから生じるパラドックスである。このラッセル・パラドックスを説明してみよう。
まず、ラッセル集合 \(R\) というものを定義する。それは「自分自身が要素とならない集合のすべてがなす集合」、つまり、次のように定義される集合である:
\(x\in x\) の様に自分自身を要素とする集合など変だと思うかもしれないが、これはラッセルの理論では自然なものだった。たとえば、自然数2の定義の条件を少し弱めて「集合 \(A\) は \(x, y\) という要素を持ち、\(x=y\) ではない」にすると、\(A\) は2個以上の要素をもつ集合となるので、これを条件として集合を定義すれば2個以上の要素をもつすべての集合の集合が定義できるが、もちろん、その集合は2個以上の要素を持つので、自分自身の要素となる。気持ちは悪いが論理に従えばこの様になる。
ところが、こういう風な気持ちの悪さがない筈の「自分自身を要素として持たない集合」ばかり集めたラッセル集合が問題を引き起こす。矛盾が論理的に証明できるのである。
背理法を使う。背理法の仮定として \(R\in R\) と仮定する。そうすると、右辺の \(R\) の定義 \(R=\{x|\, x\in x\) ではない\(\}\) から、左辺の \(R\) は、その定義条件「\(x\in x\) ではない」を満たすはずなので「\(R\in R\) ではない」となる。しかし、これは背理法の仮定 \(R\in R\) に反する。よって、背理法により「\(R\in R\) ではない」が証明された。
ところが、この結論「\(R\in R\) ではない」は、\(R\) が \(R\) の定義条件「\(x\in x\) ではない」を満たしていることを意味する。よって、\(R\in R\) である。これで「\(R\in R\) ではない」と \(R\in R\) の両方が証明できた。よって、論理学は矛盾している。
ラッセルは、この自身が発見したパラドックスも何かの勘違いの類だと信じ、簡単に解決できるものと期待してPoMをパラドックス付きで出版した。しかし、それは間違いだったのである。彼は様々な努力の末、PoM の理論は放棄するしかないと悟り、新しい理論、つまり、PM の理論を構築することになった。
その長い道のりは、PoM 執筆の時代の知的恍惚とは正反対のものであり、彼はロンドンの鉄道の上にかかる陸橋から下に飛び降りたい衝動にかられたこともあると自伝に記している。そして、十数年の苦闘の上に完成したPMでは、論理は複雑怪奇になり、また、結局は論理だけから自然数を作り出すことはできなくなり、デーデキントのような認識論的議論を使うこともできなかったので、無限集合は存在すると最初から公理として仮定するしかなかった。
とはいうものの、PM では PoM と同様に数学の殆どを再現することができた。そして、カントルのパラドックスやラッセルのパラドックスを再現することはできないように論理にブレーキが仕組まれていた。その出版後100年以上たった現在でもPMの矛盾は発見されていない。史上最初の「数学の万物の理論」が完成したのである。
14. ヒルベルト無矛盾性証明計画のルーツ
前節までで描き出した様な経緯で、「数学の万物の理論」PMが登場した。それは主にイギリスで起きた歴史であったが、実は並行してドイツで同じような動きが進行していた。そして、それがヒルベルトの無矛盾性証明計画を生んだのである。
先にヒルベルトの23の問題の第2問題は実数の理論の無矛盾性の証明だったと書いた。実は、その問題の解説の最後には、カントルの超限基数論の無矛盾性についての言及があり、実数の無矛盾性と同じように証明できるだろう、と書かれている。
ヒルベルトはカントルから彼のパラドックスを最初に聞いた人かもしれない。カントルからヒルベルトへパラドックスを知らせる書簡が残っているのである。そのころのヒルベルトはデーデキント、リーマンの新数学スタイルを継承して、彼らの地でもあるゲッチンゲンで、集合を使う抽象数学で、伝統的数学を書き変え大きく発展させる壮大な運動を彼の多くの弟子や同僚たちと共に推し進めていた。その最中に運動の要のツール、集合論のほころびが見つかったのである。
実はヒルベルトが、彼の23の問題を公表した1900年の数年前に、 ZFC のZで、彼の同僚であるエルンスト・ツェルメロ Ernst Zermelo が、ラッセル・パラドックスと同じものを発見している。他にもパラドックスは幾つか発見され、ゲッチンゲンの地では、広く数学者・哲学者の間で共有されていたのである。ただ、それは公表されず、ツェルメロが本当に、先に「ラッセル・パラドックス」を発見していたことの史料的証拠が発見されたのは、ツェルメロと非常に近い関係にあった哲学者フッサールの遺稿集の編纂の過程でのことで、1980年代のことだった(ちなみにフッサール遺稿集編纂の作業は現在も続いている)。
当初、ヒルベルトは、カントルやツェルメロのパラドックスは哲学の問題で数学には関係ないと思ったようだが、自分自身が使いたい証明方法でもパラドックスが生じることを発見して、これを真剣に考えるようになった。その結果、第2問題の付随コメントが書かれたのである。
ヒルベルトは数学の理論が無矛盾であることを、数学的に証明することにより、この危機を乗り越えようとした。その背景には、彼の集合を使う抽象数学の思想的背景である公理論という考え方があり、ある数学的対象は、その理論がいくつかの公理で明瞭に記述出来て、その公理たちが無矛盾であることを数学的に証明できれば、その数学的対象は存在すると考えてよいという、非常にモダンな考え方であった。
ただ、この公理論は幾何学などには有効に使えたのであるが、公理論自体が集合論を使っていたので、第10節の第2不完全性定理のところで説明した様な理由で、これを使っての無矛盾性の証明は上手く機能しなかった。しかも、1900年には、PMはおろかPoMさえなかった。この後、数年、ヒルベルトは自分が置かれている状況を正確に理解できず、かなり迷走をしている。そして、その後、物理学研究などが忙しくなり、数学の無矛盾性の証明はアインシュタインの一般相対性理論が発表され、また、第1次世界大戦が終結して、彼の学生たちが戦場からゲッチンゲンに戻ってくるまで棚ざらしとなっていた。
幸いなことに、この棚ざらしの期間に、PMが出版され、ヒルベルトの無矛盾性証明の意味がほとんど数学的に明確に表現できる様になった。ラッセルにその意図はなかったが、PMの命題はゲーデル数のところで見たように記号列とみなせた。また、証明も記号列で、その証明を正しい推論で作り出す方法は数学的立場からも極めて明瞭に定式化できたのである。それには集合論の様なものは必要なかった。
そこでヒルベルトは、記号列についての有限的思考方法だけを使って、PM の様な「数学の万物の理論」が無矛盾だと証明するという計画を立てたのである。この「記号列についての有限的思考方法」は「有限の立場」と名付けられ、「有限の立場でPMの様な理論の無矛盾性を証明する」という、ヒルベルト計画の大目標の一つが成立したのである。
以上がヒルベルトの無矛盾性証明計画の成立の歴史である。では、もう一つの大目標「完全性証明の計画」のルーツは何だろうか。それには、ツェルメロのパラドックスの発見の歴史的証拠が哲学者フッサールの遺稿の編纂過程で発見されたことに象徴される、19世紀の哲学と数学の今からは理解できないような親密な関係がある。
これを解明することが本サイトで紹介する私の研究のコア部分だった。私の研究によると、ヒルベルトの完全性証明の計画の背景には、ホーキングが第1不完全性定理にからめて考えた「物理学の万物の理論」の様な物理学の完全な理論についての19世紀ドイツのある有名な論争がある。そして、不完全性定理は、19世紀には有名だったが、いつしか忘れられていたその論争が舞い戻ってきたものの様にもみえるのである。ヒルベルトの完全性問題の背景には、そういうまるで因縁話のような歴史がある、というのが私の結論なのである。不完全性定理への入門で、これに深く立ち入ることはできないが、次にこれの概略の話をしよう。
15. ヒルベルト完全性証明計画のルーツ:19世紀の数学・科学・哲学
ヒルベルトの完全性証明計画のルーツ、それは、意外にも数学とは直接の関係がない、ドイツの生理学者エミール・デュ・ボア・レイモンの不可知論、正確には、それへの反感である。この忘れられた巨人デュ・ボア・レイモンは、エネルギー保存則で知られる友人ヘルムホルツとともに、19世紀の新進科学である物理学的生理学に大きな貢献をした人で、ベルリン大学長やベルリン・アカデミー長をつとめ、宰相ビスマルクを擁護する演説をするなど、大きな社会的影響力も持った人であった。
相対論や量子力学以前、多くの人たちは古典物理学という「万物の理論」を手にしていると考えた。それを使えばデュ・ボア・レイモンが自身で作成した電磁気装置でやって見せたように動物の神経の働きさえ解明できる。フランスの学者ラプラスが言ったように「現在の物理状況のすべてのデータを集める能力さえあれば、未来は完全に予測できる」と信じたのである。そういう事ができる存在は「ラプラスの悪魔」と呼ばれている。
この「ラプラスの悪魔」という言葉の由来がデュ・ボア・レイモンの不可知論だと言われる。もっとも、彼はそれを「ラプラスのガイスト(精神、霊)」と呼び、後に「ラプラスといわず、ライプニッツと言うべきだった」とも言っているが。
興味深いことにデュ・ボア・レイモンはこの「ラプラスの悪魔」のたとえを縦横に使って、逆に人類の知の限界を説いたのである。実はホーキングが1988年の著書「ホーキング宇宙を語る」で、それに似た議論をしている。ホーキングによればラプラスの悪魔には二つの不完全性がある。ひとつには悪魔が世界理解に使う法則が、なぜこの世界の法則として選ばれたのか、その法則自体では説明できない。自己参照になるからである。また、宇宙の歴史を知るために悪魔は宇宙の初期状態を知らねばならないが、現状のデータを集めることができるだけの悪魔にその能力はない。
デュ・ボア・レイモンは、これとほぼ同じ議論をして物理法則の由来や宇宙の初期状態の解明不可能性を議論した。しかし、彼は何故その様な議論をしたのだろうか。一つには新進科学の研究者として乏しい研究資金に悩み、公開実験をするなどポピューラー・サイエンスの様なことをやって資金を稼ぐ必要があったとも言われている。彼は一般向けの講演や公開実験の名手であったという。
しかし、こういう哲学の様な議論を、その時代を代表するような自然科学者が行ったことの背景には、そういう事情とは違う、現在からは想像できない哲学と自然科学や数学との関係があった。そして、その関係は「哲学の国」ドイツでは、他国に増して大きな社会的影響をもっていたのである。
ドイツの18世紀-19世紀初頭は哲学の時代だった。特にヘーゲルの存在は大きく、そしてヘーゲルは数や量の概念などについても哲学の立場から意見を述べた。リーマンの1854年の「幾何学の基礎をなす仮説について」の時代でさえ、この教授資格請求のための講演の聴衆(審査員)の多くは哲学者だった。ゲッチンゲン大学哲学部が数学自然科学部と哲学部に分かれたのは、その70年近く後の1922年の事だったからである。
しかし、ビスマルクの時代、多くの王国に分断されていたドイツの統一がなされドイツ帝国が生まれた19世紀後半にいたると、急速な近代化が始まる。その結果、哲学が自然科学により置き換えられる様になる。たとえば人文学だった心理学に実験が持ち込まれ実験心理学が生まれたのはこの頃である。またヘルムホルツは彼の物理学的生理学を使ってカント哲学の真偽を研究しようとさえした。
この置き換えは自然科学が哲学を押しのけるという単純なものではなかった。両者の複雑なインタラクションが起きたのである。ヘルムホルツの例の様に、それまでは哲学でしか議論できなかった事を、自然科学で議論する様になったということは、哲学が占めていた領域に自然科学が分け入り始めということである。その結果、ヘルムホルツがそうしようとしたように、逆に、自然科学者の中に哲学的議論をする人が少なからず出て来たのである。と言うより、自然科学は元々は自然哲学だったのである。
このため、19世紀には、現代ならば哲学者でないと行わない様な議論や研究が科学者や数学者により盛んに行われていたのである。実際、哲学を科学しようとしたヘルムホルツや、実験心理学の祖のヴントは哲学者としても知られている。この時、自然科学と哲学は、その境界で入り混じっていたのである。
そして、デュ・ボア・レイモンは、そういう時代に自然科学への過剰な期待に警告を発するため、自然科学者でありながら、哲学的議論で自然科学の限界を説いたのである。そして、その不可知論のモットーが「我々は知らない。我々は知らないであろう」だった。
このデュ・ボア・レイモンの不可知論の意図は、生命の無い物の学の物理学が、彼やヘルムホルツの物理学的生理学により、「命を持つもの」「魂を持つもの」の領域に踏み込んでしまったために、当然の様に起きる彼らの唯物論的・実証主義的な世界観と、生命には魂のような「生気」が宿るとする「生気論」の様な世界観との間に境界線を引き、自然科学者がその研究を進める際に哲学的論争に煩わされない様にするためだったと考えられている。
つまり、自然科学は、これ以上は哲学に領空侵犯はしないので、そちらからの攻撃も止めて欲しい。科学者のみんなも、この線からは出ないようにしようという呼びかけだったと思われるのである。
しかし、若き日のヒルベルトはこの不可知論に強い敵意を持ち、少なくとも数学ではそういうことは起きないということを数学で証明するという計画をたてた。数学を深く愛した彼は、自然科学と異なり、数学には限界がないと考えたのである。そして、それが後にヒルベルト計画の完全性証明の計画となったのである。
このサイトの「ヒルベルト数学ノートブックの研究」で示しつつあるように、彼は、まだ無名と言ってよかった若き日、その数学ノートブックにカント哲学などについてのメモを繰り返し書いた。たとえば、「カントは正しい。しかし、中途半端だった。自分は、それを数学的に証明するべきだ」という意味のことを書いている(そのノートの画像と、翻刻、和訳、分析は、こちら)。そして、それが数学は完全である。すべての数学の問題は解決できるという完全性のことだったのである。そして、「ヒルベルト数学ノートブックの研究」の3.3.5で議論するように、このメモの後、ヒルベルトは「哲学的議論でなく、数学的議論で『数学の哲学』をする」というスタンスで、数学の基礎の理論、数学基礎論に関わって行ったのであり、その研究目標の定式化の完成形が、1920年代のヒルベルト計画だったのである。
実は、ヒルベルトの物理学研究のルーツも、この様な関わりの一環であったらしく、物理学を様々に公理化して、その内で最善の理論が現在の物理学理論に一致することを示すという野望にあった。つまり、数学は物理学と違う、数学に関する哲学的問題も数学ならば解決できるというだけでなく、自分が生み出した公理論という新しい数学を使えば、デュ・ボア・レイモンが説いた物理学理論の由来の不可知という限界さえも突破できるというのである。ただ、その計画を書いたノート(メモ)は、特殊相対論以前のもので、その物理学とは古典物理学のことであった。特殊相対性理論の後に開始されたヒルベルトの物理学研究の目的の中に、若き日の哲学的野望が秘められていたのかどうかはわからない。
デュ・ボア・レイモンの古典物理学の万物の理論についての不可知論への反発がヒルベルト計画を生み、そして、それがデュ・ボア・レイモンの議論にどこか似たゲーデルの議論で否定されてしまった。何か輪廻・因果応報を感じさせるような話である。
ちなみに、ヒルベルトの1930年の「我々は知るであろう。知らねばならない」は、もちろん、デュ・ボア・レイモンの「我々は知らない。我々は知らないであろう」を裏返して見せたものだった。この有名な「勝利宣言」の前日、同じ学会の会場で、第1不完全性定理をノイマンが知ったというのも何か因縁めいている。
16. 不完全性定理のインパクト
最後に、不完全性定理が、いままで書いてきた様な、哲学と数学の境界地帯でのせめぎあいにどの様な影響を与えたかを説明して、このテキストを終わろう。
ラッセルによる最初の「数学の万物の理論」以前には、数学と哲学の境界線は実に不分明だった。実は、リーマンは自身を自然哲学者と考えており、彼の理論の背景には「魂」の概念が絡む自然哲学があった。また、哲学においては、たとえばPoMでラッセルが酷評した新カント派マールブルグ学派の哲学者ヘルマン・コーエンの「無限小の哲学」の様なものがあった。その主たる目的は数学の哲学ではなくて、無限小をベースにした存在論・形而上学の様なものだったのである。
リーマンやコーエンは、哲学・数学が地続きのものと考えて、リーマンは哲学を背景に数学を行った。その天才的直観は現在の数学の範囲を超えるもので、ディリクレ原理の様に時としてそれを踏み外してしまうこともあったが、数学において使った哲学は後にラッセル達により完全に数学化される論理学だけであった。そして、集合論の数学における受容により、その論理学も集合として完全に数学に併合された。
一方、コーエンは数学の概念をインスピレーションの源泉としてのみでなく、それを哲学の基礎として、哲学を行った。20世紀の後半でもフランス現代思想などを中心に、不完全性定理から哲学的結論を引き出そうとする人が後を絶たなかったが、これと同じようなものである。
もちろん、その様な哲学を行うことは哲学者の勝手であり、特にインスピレーションのために数学を利用するのは全く構わないとおもうが、それにより、その哲学に数学や科学の合理性が宿るわけではない。むしろ、それは逆であろう。数学者や自然科学者は、自分たちの学問が哲学者にもてあそばれることにフラストレーションを感じ勝ちのようだが、同じ言葉で全く別のものについて語っているのだと割り切って距離を置くべきだろう。
しかし、「数学を背景とする哲学」には、このコーエンや20世紀フランス現代思想とは全く異なる別のパターンがある。それがヒルベルトの哲学への関わりだったのである。
ヒルベルトはカントがその生涯を過ごした東プロイセンの古都ケーニヒスベルクで生まれ育ち、この街を愛し先人カントを尊敬した。そして、若きヒルベルトは哲学的問題に強い関心をもった。そして、その中心は数学の理論の完全性を証明することだった。
しかし、ヒルベルトは哲学的手法、つまり、哲学的思索には全くと言って良いほど興味をしめしていない。彼の著作、遺稿には、哲学的議論というものがほぼないのである。彼は1930年の講演「自然認識と論理」で、哲学者の名前とその問題意識を引用しながらも、数学の基礎を巡る彼の論敵たちを「数学者の服を着た哲学者」とまで呼んでいる。哲学者に対してあまり尊敬の意を感じない発言である。
これは一見、若き日の彼の哲学的問題への興味、それのヒルベルト計画としての実行と矛盾している様に見えるが、そうではない。ヒルベルトは哲学の手法、つまり、哲学的考察や議論は不明確で根拠のないものと考えたと思われるが、その問題には興味を持ち、そして、厳密な数学でその問題を解決できると考えたのである。それがヒルベルト計画だった。
現在から考えれば、数学者が哲学的問題に手を出すなど、しかも数学的手法で手を出すなど、デュ・ボア・レイモンの境界線を超える危険かつ無謀な行為にみえるが、ヒルベルトの青春時代、「物理学の帝国宰相」とさえ呼ばれたヘルムホルツの様な人物も行っていたことなのだから、若いヒルベルトが同じようなことを考えても不思議ではないのである。
1920年代、ヒルベルト計画が進行していたころ、すでにこういう姿勢は古いものとなりつつあり、デュ・ボア・レイモンの境界線の方が市民権を得つつあった。しかし、もしヒルベルト計画が本当に成功していれば事情は大きく違っていただろう。数学の基礎に対して敬して遠ざけるようなノイマンの最後の立場を採る数学者は少なかったかもしれない。
しかし、二つの不完全性定理により完全で無矛盾だと保証された数学の万物の理論という哲学的理想は永遠に葬りさられた。それをいち早く悟ったノイマンは、さっさっと古い考え方を捨て、ZFC, NBG などの存在で数学の基礎はじゅうぶんだと考えるようになり、それを基礎に様々な数学研究を行うだけでなく、コンピュータ、原爆の開発にも関与するというモダンな姿勢に転換してしまった。
そして、彼以後の数学者のほとんどは、不完全性定理の存在により、最初から、哲学と数学の国境に近寄ろうとさえしない。多くの数学者は、国境線を垣間見たことさえないのである。PM, ZFC, NBGにより論理学という哲学の旧領地は、現在はすっかり数学に併合されてしまっているからである。
ヒルベルト計画も、いつか聞いたことがある、朧げな記憶の昔話に過ぎない。この様な数学者の哲学への態度の大きな変化をもたらしたこと。それがゲーデルの二つの不完全性定理の人類の知の歴史における最大の意義なのである。
注1.ホーキングが「ゲーデルと物理学の終」で、不完全性定理の故に(物理学の)万物の理論は不可能だと主張したという意見があるようだが、それらはホーキングの意図を誤解している。講演の記録の最後の部分には "Goedels theorem ensured there would always be a job for mathematicians. I think M theory will do the same for physicists." 「ゲーデルの定理は数学者が失業しないことを保証している。私はM理論が同じように物理学者が失業しないと保証してくるだろうと考えている」という文がある。数学者や物理学者が失業しないとは「完全な理論ができて学者がすることが無くなる、ということはない」という意味だが、数学の場合は、それを保証してくれたのはゲーデルの定理だが、物理学では万物の理論の最有力候補のM理論がそれを保証してくれるだろう、とホーキングは言っているのである。つまり、まだ「物理学の不完全性定理」は証明されておらず、しかも、証明できるとしたら、物理学の理論であるM理論によってだろうと言っているのであって、不完全性定理が物理学の不完全性を証明するとは言っていないのである。この話の詳しい所は、私のブログの三つの投稿1,2,3に書いてある。