作者の自己紹介
自己紹介
2024年5月6日追加:私への連絡には次をお使いください。ただし、存じ上げない方には、ほとんど返事をしませんので、どうか悪しからず。
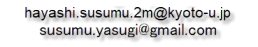
本名 八杉晋(やすぎ すすむ)、旧姓は林です。文章を書いたり講演をしたりの仕事の際には主に旧姓を使っています。元京都大学文学研究科教授で京都大学名誉教授および神戸大学名誉教授です。2019年3月末に京大を定年退職して以後は主に主夫業をしています。経歴と業績は、こちらをご覧ください。
わたしが中学生のころ論理・集合が中等教育に持ち込むアメリカの数学教育改革運動 ニューマス(New Math) が日本にも輸入され始めました。数学の授業で最初に証明というものに出会ったときに「こういうものの考え方があるのか」と大きな衝撃を受けて、幾何の証明問題を解く時に図を全く使わず言葉と数式だけで解くことにこだわる様な中学生だった私は、このニューマスに惹かれ、岩波新書のニューマス本を数学教師に教えてもらい読んだりしていました。そのニューマスの影響もあったのかもしれませんが、高校生の時、日本語で初めて不完全性定理の解説本が出版され、それが書店で平積みになっているのを偶々手にし、それが切っ掛けになって数理論理学を志すようになりました。要するに理屈・論証・論理がフェチ的に好きだったのです。そして、その性格がその後のキャリアを決めたといえます。ただ、論理を深く理解できるようになって、その限界が良く見えるようになり、論理自身に対する私の態度は大きく変わったのですが。
高校生のころは論理や数学、時に哲学の本ばかり読んでいて受験勉強は全くしないという風だったので、大学進学はしないつもりでいましたが、勝手に兄が数少ない数理論理が勉強できる私学の受験の書類をいくつか取り寄せてくれて、私もその気になり2か月ほど赤本を解いて、結局、その当時日本国内では最大級の数理論理学と数学史関係の教員団があった立教大学の数学科に入ることができました。その後、大学院の後期は筑波大学の数学研究科に移り、そこで学位を得たものの数理論理学では職が無く、そういう場合の当時の定石として情報分野に転じました。その後、色々な大学を転々として最初はソフトウェアの科学への数理論理学・数学の応用、後にはソフトウェアの生産ための工学であるソフトウェア工学に携わっていましたが、幸運が続いて五十歳代になって修士論文を書き終えたころに一度試みて失敗した歴史学(数学史)への転向に成功し(その経緯を書いたエッセイふたつ)、その後は歴史学を中心とする文系の学者・教育者としてすごし2019年3月に京大を定年退職しました。
理系の人が学生時代に文系に転じることは昔からよくあり「文転」と言いますが、私の場合は五十歳代になって、しかも理系でそれなりのキャリアを積んでのことなので珍しがられました。ある知人などは「何があったのですか」と心配そうに聞いてくれたものです。その本当に心配そうな表情を見て、この人本当に良い人なのだなと思ったものです。多分、林が何かのスキャンダルでも起こして違う分野に転身せざるを得ないではないのかとでも思ったのでしょう。もちろん、予想もしない幸運の連続で長年の夢がかなった私自身はその正反対でルンルンだったわけですが。
14年間、文系の教授として教育に携わり、またそれ以前の理系の期間を含めれば40年近くも大学教育に携わりました。その間、40歳台終わりごろからだと思いますが、若い人たちが自分では理解できていない才能を客観的に理解することができるようになったものです。その様になると、若い人の才能と成りたいものは一致してないことがままあることが見えるようになります。そして、そういう現在の私から自分の若いころを見れば、明らかに理系よりは文系に才能があったことがわかります。私は自分は文系の才能はない自分は理系だと子供のころから信じ切っていましたが、数学などは苦労して苦労してやっても常に壁が前に立ちはだかっているのですが、文系の仕事、たとえばエッセイ書きなどをたまにすると、えっ、どうして自分はこういう文章が書けるのか!?と自分で驚くほど楽々と色々なことが自然にできてしまっていたのです。もし若いころの私に助言するとしたら「林君、君は理系よりは文系の学者になった方が良いのではないですか」と言いたいところです。実際、才能だけでなくて、数学をやっているときはわからないことが多くてつらかったわけですが、情報に移ったら自分が書いたプログラムが走るのが楽しいのでかなり気が楽になったものの、それでもそれなりに限界を感じて苦しかったものです。ところが、本当にやれるのか実はかなり心配だった文系に移ってみると、全然苦しくないのです。
もちろん労力としては大変で、特に特殊講義という毎年新しい研究を講義する科目は本当に準備が大変で「今度の講義、間に合うかな」とハラハラしたことは良くありました。ところが、それが楽しいのです。色々な講義をしましたが、ある哲学とは全く関係ない経緯で(その経緯:この講演のスライド8-12)日本哲学史の講義を行うこと(はめ?)になった際でさえ、わけのわからない文章が、ポイントをマークアップしながら細かく分析していくと、いつの間にか読めるようになり、著者の錯綜する思索の道筋やその背景の心の動きまで読めてしまうのです。
思想史・哲学史に限らず歴史学一般でそうなのですが、こういう作業に近いのはスリラーのドラマや映画で刑事が行う謎解きです。私の場合のように、まだ研究対象の史料群が十分定まっておらず、それの発掘から始めるのが当然の近現代史の研究者の場合は、注目されていない史料、埋もれている史料の中に謎を解く「証拠」を見つけるのが重要な仕事となります。これがなぜかホイホイできてしまうのです。最初は、これは素人が誤解して、出来てもないのに出来たつもりで勝手にやっているだけなのではないかと心配して、同僚の現代史の人に相談したりしましたが、どうもまともに出来ている。それで振り返ってみれば、そういう能力が確かに高いようで、ただ理系の時代には、そういう史料を読む能力が理系の仕事に役立つことはないので(ただ一度だけLCMというものを作る時には役立ちましたが)、それに気が付かなかっただけだったと分かったのです。
とはいうものの、本当に自分の歴史学の才能・知識は本物なのかということはずっと気になっていました。私がやっていた研究は、数学や哲学、それに関連する工学などの歴史ですが、そういう関係の歴史学として知られる数学史・科学史・技術史は歴史学の本流の研究の仕方とはどうも違うような気がして、そういう関係の学会などからは意図的に距離を取っていました。一方で、対象がそういうものだと一般の史学の学会などには馴染まないため、そちらの学会に出るというようなこともありませんでした。そのため自分が歴史学者としてまともなのかということは、ずっと気になっていたのです。ところが、定年退職を迎える直前に研究室の再編を行った関係で最後の年度だけ、現代史のセミナーに出たり、現代史の修論や博論の審査も手伝う様になったのですが、その際、私のセミナーなどでのコメントを見聞きした優秀な現代政治史の同僚が「もっと早くからセミナーに出てもらえばよかった」と言ってくれたことと、現代史研究者の同僚たちのコメントが自分の意見やコメントとそっくりなことを見てようやく「やってきたことは大丈夫だったようだ」と思ったものです。
この様に大変な回り道をした学者人生でしたが、理系への回り道をしなければ、理系には天与の才能がなかっただけに、このWEBサイトで紹介するような研究はできなかったでしょう。壁に苦しみながらも数学や情報学をやっていたのは、今から見れば大変重要な準備期間だったと言えます。そんな風で全体としては実に充実した楽しい学者人生だったといえます。そして、そういう道を経て私が最後に到達できた「解答」を紹介しようというのがこのWEBサイトであるわけです。